相続手続きでは、相続人を確定させるために市区町村役場で被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍や、相続人の戸籍や住民票などが必要となります。
遺産分割協議が完了して、相続財産の名義変更をする際に、各窓口で戸籍を持参して、相続人である旨の証明をしないと手続きをすることができません。
戸籍はとても重要な情報が記載されているため、手続きをする際に、戸籍の記載内容を全て見せたくない場合や、戸籍の束をもっていくと紛失の可能性もあり心配な場合、各相続人が戸籍を複数取得していない場合など、様々な事情もあると思います。
そういったケースでは、法定相続情報証明制度を活用すれば、問題を解決することができます。
今回の記事では、法定相続情報証明制度について解説していきたいと思います。
法定相続情報証明制度とは

身近な人が亡くなった場合に、親族は相続手続きを行わなくてはなりません。
身近な方が亡くなったらまず戸籍を集め、相続人を確定して被相続人の財産を調査して、その内容で遺産分割協議を行います。
その後、不動産や預貯金があれば、金融機関や法務局に出向き、預金の払い出しや、不動産の名義変更のため、相続登記を行いますが、その手続きには戸籍と遺産分割協議書が必要となります。
金融機関に提出する戸籍は量も多く、その確認には時間がかかりますし、金融機関に戸籍を提示する事になります。
そういった時に法定相続情報一覧図の写しを法務局で交付してもらうと、その後の相続登記や金融機関などの手続きが大変楽になります。
広告
法定相続情報証明制度ができた背景

法定相続情報証明制度が運用されるようになったきっかけは、所有者不明土地や空き家が社会問題となり、その問題を少しでも解決するため、この制度ができました。
何故空き家などの問題が増えてきたのでしょうか。
それは、相続人が相続登記などをしないで、そのまま放置してしまうケースがあるからです。(令和6年4月1日に相続登記は義務化されます)
相続手続きはとても煩雑で戸籍を集めるのも苦労します。
そのため、相続手続きを放置して、時間が経過して、財産を承継するはずだった相続人が亡くなりさらに相続人が増えることになり、相続人を特定したり、相続人全員の合意を得ることがさらに難しくなり、余計に手続きを終了させるのが困難になり、登記簿上の所有者と真の所有者が異なる不動産が増えてきたのではないでしょうか。
上記のような、煩雑な相続手続きを簡略化するため、法定相続情報証明制度ができました。
この制度は、相続財産のなかに不動産がなくても利用することができますので、預貯金の払戻しのみでもこの制度を活用できます。
法制相続情報証明制度の利用手数料は無料となっておりますので、戸籍のみを集めることができれば、どなたでも無料でこのサービスを受ける事ができます。
法定相続情報制度で必要な書類

法定相続情報証明制度を利用するには管轄の法務局で申出をする必要があります。
申出を行うときは、申出書を作成して、相続関係を証明するため、戸籍などを添付する必要があります。
被相続人に関する書類
- 被相続人の最後の住所を証する書面
- 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者の分も必要です)の出生時から戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
相続人に関する書類
- 相続人の戸籍謄本(抄本)又は記載事項証明書
- 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを称する書面
- 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書
- 法定相続相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときはその住所を証する書面
申出人が作成する書類
- 法定相続情報一覧図
- 代理人が申出をするときには、当該代理人の権限を称する書面
広告
被相続人の住所や相続人の戸籍を取得する方法
被相続人の最後の住所を証する書面として住民票の除票か戸籍の附票を取得することになります。
戸籍の附票とは、本籍地の役所で作成される戸籍に記載されている人の住所が記載される書面のことです。
戸籍の附票に関しては、被相続人(亡くなった人)の本籍地の役所で取得してください。
住民票の除票とは
住民票の除票とは、除かれた住民票のことですが、住民票が除かれるとは、どういう意味なのでしょうか。
住民票が除かれるとは、住民票に記載されている人が転出や、亡くなった時に、住民票から除かれます。
今回の場合だと、亡くなったため、住民票から除かれることになります。
住民票の除票を取得する際には、亡くなった住所地で取得するようにしてください(本籍地戸籍の筆頭者の記載があるもの)
住民票の除票は、郵送でも窓口でも取得することが可能です。
相続人が住民票を取得する際には、被相続人の戸籍が必要になるかと思いますので、ご自身でお手続きをする際には、役所に確認してから取得するようにしてください。
住民票の除票は、保存期間の経過で廃棄され発行されない事もありますが、その時は廃棄証明が取得できるようなら取得して、本籍地で戸籍の附票を請求するようにしてください。
法定相続情報証明制度で提出する申出書

法定相続情報証明制度には、被相続人や相続人の、戸籍や、住民票が必要となりますが、その他にも法定相続証明情報を利用する際に必要となる申出書を作成しなくてはなりません。
申出書は何を記載したらよいのか
申出書には、下記の事項を記載します。
- 申出人の表示
- 代理人の表示
- 利用目的
- 必要な写しの通数・交付方法
- 被相続人名義の不動産の有無
- 申出先登記所の種別
申出人の表示とは
申出人には、相続人や当該相続人の地位を相続により承継した者がなれます。
主に法定相続情報証明制度は相続人が活用する制度のため、問題はないかと思いますが、相続人が請求する場合でも、書面で確認できる相続人となっています。
胎児や認知されていない相続人は戸籍に記載がないため 、本来は相続人でも戸籍に記載されていないため、申出人となることはできません。
相続人の地位を承継した者とは、数次相続などのことです。
数次相続が発生した場合には、少し面倒ですが被相続人ごとに別々の一覧図を作成する必要があるため、戸籍収集の手続きや一覧図を作成することが難しくなります。
広告
法定相続情報証明制度の申出書の書き方
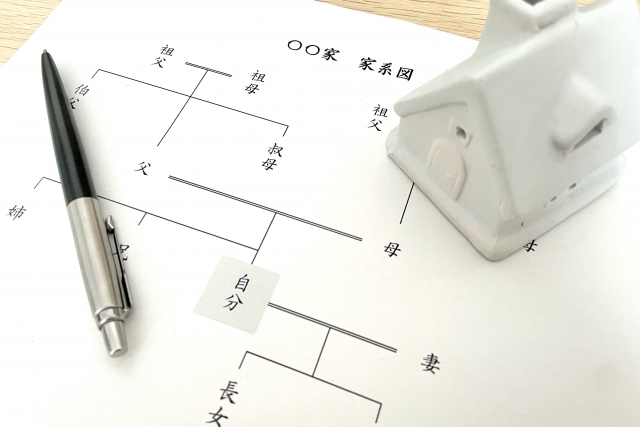
法定相続情報証明制度を活用するためには、戸籍、申出書、一覧図を管轄の法務局に提出することによって、利用することができます。
申出書の記載事項である利用目的は何を記載すればよいか
法定相続情報証明制度は、相続登記や金融機関などの相続手続きにおける相続人の負担の軽減のために導入された制度のため、利用目的は、あくまで相続手続きで使用するものでなくてはなりません。
そのため、家系図の作成のために法定相続情報証明制度を活用することはできないということになります。
利用目的は、申出書にチェック欄があるため、基本的にはその部分にチェックを入れれば問題はありませんが、チェック欄がない場合は、その他にチェックをいれて、相続手続きの何に使うのかを記載するようにしてください。
必要な写しの通数・交付方法はどう記載すればよいのか
申出書に法定相続情報証明制度で最終的に法務局で発行してもらう一覧図の写しを交付してもらいますが、何通交付するのかを申出書に記載します。
一覧図の写しは、金融機関での預金の払戻しなど、相続手続きで使用するため、利用目的に照らして、必要な通数を交付してもらうことが可能ですが、通数が適切かどうかは、利用目的で法務局が判断します。
一覧図の写しは、窓口でも郵送でも貰うことができます。
法務局が近くにある場合は、窓口で受領するのもいいかもしれませんが、法務局で戸籍を確認してから発行になるため、即日発行できません。
そのため、基本的には郵送で受け取るようにした方が良いかと思います。
郵送で受け取る際には、返信用封筒を忘れないようにしてください。
不動産の所在事項の書き方
申出書に記載する不動産の所在事項の書き方でお困りの方もいらっしゃるかと思います。
不動産の所在とは、住所のことではなく、法務局で不動産を特定するときに使うものです。
不動産を特定するには、法務局で登記簿謄本を取得して確認をする必要があります。
申出書に記載するときは、登記簿謄本と全く同じように記載するようにしてください。
間違えそうであれば、不動産番号で特定することもできます。(不動産番号は登記簿謄本に記載してあります)
不動産が複数ある場合には、1つの不動産に関して所在事項又は不動産番号を記載すればよいですが、不動産の所在地を管轄する法務局に申出する時は、当該法務局の管轄区域内の不動産にかかる所在事項又は不動産番号を記載しなくてはいけないため、注意が必要です。
法定相続情報証明制度の一覧図の記載事項
法定相続情報証明制度を活用するときには一覧図が必要ですが、一覧図とは、相続関係を第三者がみてわかるようにした家系図だと思っていただければイメージしやすいかと思います。
一覧図には、記載しなくてはいけない事項があります。
- 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
- 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
- 法定相続一覧図の作成年月日、申出人の記名、作成者の署名又は記名、作成者の住所
一覧図の作成方法
一覧図は、A4サイズの白紙で作成します。
一覧図の作成は、一般的にパソコンで作成するものですが、手書きのものでも作成することが可能です。
ただ、一覧図にミスがあった場合に手書きだと面倒なのでパソコンで作成することをお勧めいたします。
法務局のホームページでも記載例がありますので、そちらをご覧いただければ作成しやすいと思います。
一般的にパソコンで作成するものですが、手書きのものでも作成することが可能です。
ただ、一覧図にミスがあった場合に手書きだと面倒なのでパソコンで作成することをお勧めいたします。
広告
申出人以外に書類を頼みたい場合
法定相続情報証明制度を活用できるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍から確認できる相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者が申請をすることができます。
委任状を提出すれば、親族や資格者代理人も作成することができます。
ただ、法律に詳しくない親族が、法定相続情報証明制度を活用しようとしても、書類を収集できなかったり、一覧図を作成することができないかもしれません。
法定相続情報証明制度は戸籍収集して一覧図を作成しますので、ある程度戸籍などの書類を読めないと作成するには、とても時間がかかります。
そのため、相続手続きを、行政書士や司法書士に依頼をしてその手続きの中で戸籍を収集して、法定相続情報証明制度を利用するのが一般的だと思います。
士業以外にも相続人が未成年の場合には、親権者(親)は法定代理人として書類を作成することもできますし、後見制度を利用している人は、後見人を法定代理人として作成してもらえます。
法定相続情報証明制度を利用するための管轄
法定相続情報証明制度を利用するためには、申出書、戸籍等、一覧図などが必要となります。
申出書と一覧図を作成した後に、戸籍などの申出時に添付する証明資料も全て収集したら、どの法務局に作成した書類や集めた証明資料を提出すればよいのでしょうか。
管轄法務局
- 被相続人の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
- 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する法務局
法定相続情報証明制度を提出する窓口
法定相続情報証明制度を担当する窓口は、基本的には法務局の不動産登記を担当しているところです。(専門の窓口がある法務局もあります)
法務局の管轄がわからないようであれば、近くの法務局に電話して問い合わせて確認するようにしてください。
数次相続がある場合の管轄法務局
通常上記の1~4に当てはまる法務局が管轄法務局になりますが、数次相続の場合には上記の1~4以外の法務局にも提出することが可能です。
まず数次相続の場合には、被相続人一人ずつの法定相続情報一覧図が保管されて、一覧図の写しが交付されることになります。
数次相続の管轄法務局を簡単に説明すると、例えばA→B→Cと相続が発生している場合には、Aの本籍・最後の住所が東京都新宿区、Bの本籍・最後の住所が埼玉県さいたま市であった場合には、Aの相続に関する制度利用の申出をしたのが新宿の法務局であれば、Bの相続に関する申出もさいたま地方法務局でなく、新宿の法務局で申出を行うことが可能になります。
複数の相続が発生している場合に原則通り複数の法務局で作成するのは申出人にとても負担がかかりますし、手続きが煩雑になり大変です。
広告
まとめ
相続情報証明制度を活用するためには、戸籍を集めて相続人を確定し、申出書と一覧図を作成しなくてはなりません。
慣れていないと、戸籍を集めるだけでもとても大変です。
被相続人(亡くなった人)の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の戸籍、住民票の除票など様々な書類を市区町村長役場で取得をする必要があります。
そのため、書類作成や管轄法務局で手続きが難しいようであれば、当サポートセンターに、ご相談いただければ幸いです。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。





