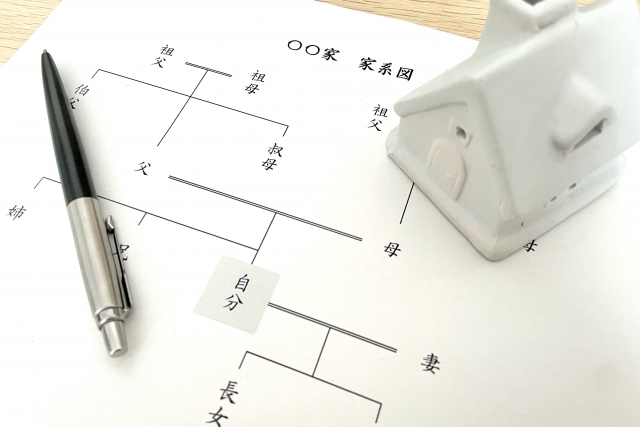人が亡くなった場合、亡くなったかたの財産などは、誰にどのように相続されるのでしょうか
遺言書がある場合と、ない場合で対応が変わりますが、基本的に遺言がない場合は相続人全員で話し合いをして、相続財産の帰属先を決めることになります。
今回の記事では、法定相続人の範囲、相続人、遺言書がない場合の相続について解説していきたいと思います。
遺言書がない場合の法定相続と相続人の相続分について

「相続」は、ある人が死亡した場合に、その人が保有していた全ての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを指します。具体的には、次のようなものが相続の対象となります。
- 現金や預貯金
- 株式等の有価証券
- 車・貴金属等の動産
- 土地・建物等の不動産
- 借入金等の債務
- 賃借権・特許権・著作権等の権利
(相続の一般的効力)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続の方法
相続の方法には、主に次の3つがあります。
- 法定相続:民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
- 遺言による相続:亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
- 遺産分割協議による相続:相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺産をもらえる人
- 法定相続人:民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
- 受遺者:遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
遺言書がない場合の法定相続の重要性
遺言書がない場合、遺産相続は法定相続人が被相続人の遺産を相続します。法定相続人とは、その名のとおり法律(民法)で決まっている相続人のことで、具体的には「配偶者」と「血族」です。
遺産を相続するといっても、遺産によっては、①相続人の全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」を必要とするものと②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとで分かれます。
①遺産分割を必要とするものとは、例えば、不動産や銀行預金(預貯金払戻請求権)、動産、有価証券などを言います。これらについては、法定相続人が遺産分割をするまでの間は、相続人の共有となり、法定相続人がそれらの遺産を単独で処分することができません。
②遺産分割をせずに法定相続分に従って当然に分割されるものとは、例えば、現金や貸付金などの金銭債権です。これらについては、遺産分割をすることなく、相続人が法定相続分の割合で遺産を取得します。
※実務上は遺産分割協議をして①、②の財産を誰が相続するか話し合いで決めます。
法定相続分が定められている趣旨は、遺族の生活を保障することや、遺言が無いために遺産相続が混乱することを避けることにあります。遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡し、さらに相続人が増えてしまうケースは珍しくありません。その場合には、遺産分割協議をすることがたいへん困難になってしまいますので、遺産分割協議をしておくことを強くおすすめします。
遺言書がない場合には、相続人で相続人調査や遺産調査を行い、遺産分割協議を行うなどしてなるべく早めに所定の手続きをとりましょう。遺言書があれば、その記載内容が法定相続分よりも優先されますが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行って分割方法などを決めることになります。
広告
相続人の決定プロセス相続人の決定について

- 法定相続人の特定:遺産相続では、民法に基づき誰が相続権を持つかが定められており、これらの人々を法定相続人と称します。被相続人が亡くなった場合、配偶者はどの状況でも民法により相続人と認定されます。親族の場合、相続の順位は被相続人との血縁関係によって決定されます。
- 相続人の調査:遺産相続を進めるためには、まず法定相続人を特定する必要があります。このプロセスは手間がかかり、被相続人の現在の戸籍からさらに遡り、出生まで遡る古い戸籍も取得する必要があります。
- 相続人の確認:相続人を確認する方法は、戸籍謄本を集め、「他に相続人がいないこと」を証明することです。
| ステップ | 説明 |
| 相続の開始 | 人が亡くなったときに始まります。亡くなった人を被相続人といいます。 |
| 法定相続人 | 被相続人の財産を受け取ることができる人たちを指します。法定相続人には、被相続人の配偶者や子ども、親などの血のつながりのある人が含まれます。 |
| 法定相続分 | 被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書に書かれていない財産がある場合は、法定相続人の中から誰がどのくらいの割合で財産を受け取るかが決まります。この割合を法定相続分といいます。 |
| 10年以上の経過 | 相続が始まってから10年以上経過した場合は、特別な事情がない限り、法定相続分に基づいて財産を分けることになります。ただし、相続人全員が同意すれば、法定相続分とは違う分配方法で財産を分けることもできます。 |
法定相続人について

日本の民法では、法定相続人は以下の4種類が存在し、それぞれには順位があります。この順位が相続における優先順位となります。
配偶者(常に相続人)
配偶者とは、故人と婚姻関係にあった夫や妻を指します。婚姻関係のない内縁の妻などには相続権はありません。配偶者は常に相続人となります。
子供(第一順位)
子供とは、血縁関係のある子供だけでなく、養子も含まれます。胎児は既に生まれているものとみなされ、相続ができますが、死産の場合は、初めから相続人にならなかったことになります。
直系尊属(第2順位)
被相続人に子供がいない場合は、直系尊属が財産を承継します。直系尊属とは、故人の父親と母親を指します。
兄弟姉妹(第3順位)
故人に子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続
本来相続すべき人が故人より先に亡くなった場合に、その人に代わって相続できる制度を代襲相続といいます。代襲相続は、子供と兄弟姉妹の場合は可能ですが、兄弟姉妹は再代襲をすることはできません。
広告
法定相続分

各法定相続人には、民法で決まった相続分があります。具体的な相続分は以下の通りです。
配偶者と子供の相続分:2分の1
配偶者と直系尊属の相続分:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹の相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4
例えば、故人に配偶者と3人の子供がいる場合、法定相続分は以下の通りです。
配偶者:1/2
各子供:1/6 したがって、故人が600万円を残した場合、相続分は以下の通りになります。
配偶者:600万円 × 1/2 = 300万円
各子供:600万円 × 1/6 = 100万円
(法定相続分)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
まとめ
相続は複雑な手続きが必要で、遺言がない場合は法定相続分に従って進められます。しかし、私たち行政書士のサポートにより、遺産分割協議を円滑に進め、財産の承継を柔軟に行うことが可能です。また、戸籍の調査や財産の調査も行います。相続手続きにお困りの方、安心してお任せください。私たちはプロフェッショナルとして、皆様の相続問題を解決いたします。お気軽にご相談ください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は責任を負いかねます。