遺言書を作成する際に重要なポイントとして「非嫡出子の認知」があります。非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子供)は、父親との親子関係が自動的に成立せず、認知を通じて法的に認めてもらう必要があります。この記事では、遺言による非嫡出子の認知方法を、法的な観点から詳しく解説していきます。
遺言で非嫡出子を認知するとは?

非嫡出子を遺言で認知することは、父親の意思を法的に明確にし、子供の権利を確保するために重要な手段です。この章では、そもそも「非嫡出子」とは何か、そして認知がなぜ必要なのかについて、基本的な理解を深めていきましょう。
非嫡出子の定義と認知の必要性
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を指します。通常、婚姻している夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」として法律上の父子関係が自動的に成立しますが、婚姻していない場合、父親が積極的に認知を行わなければ、法律上の親子関係は認められません。
認知を行わない限り、非嫡出子は父親の相続人となることができず、法的な保護も受けられません。したがって、非嫡出子がいる場合は、父親としての責任を果たし、将来の相続トラブルを避けるために認知を行うことが重要です。
遺言による認知のメリット
認知には、生前に行う方法と、遺言によって死後に行う方法の2つがあります。生前に認知を行う場合は、市区町村役場で認知届を提出しますが、家庭の事情などで生前に認知を公にするのが難しいケースも少なくありません。
そこで、遺言による認知が有効な手段として考えられます。父親が生前に認知を行わず、遺言書で認知の意思を明記することで、父親の死後に非嫡出子が法的に認知され、相続権が確定します。遺言による認知は、家族間のトラブルや財産分割の問題を回避しつつ、非嫡出子の権利を守る方法として有効です。
広告
遺言で非嫡出子を認知する手順
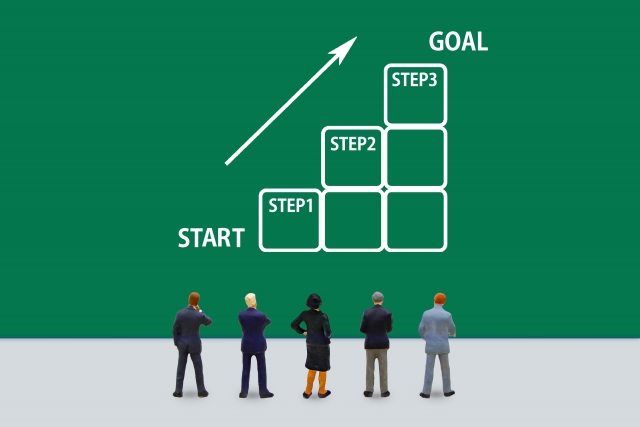
遺言で非嫡出子を認知するには、いくつかの法的手続きと形式上の要件をクリアする必要があります。ここでは、具体的にどのような内容を遺言書に記載すべきか、どの形式の遺言が適しているのか、行政書士に依頼する際の流れや費用感など、実務に役立つポイントを詳しく解説します。
遺言書に記載する内容|認知の意思と遺言執行者の指定
遺言書を用いて非嫡出子を認知する場合、遺言書には次の事項を明確に記載する必要があります。
- 認知する子供の氏名
- 子供の生年月日
- 認知の意思を示す文言
例えば、「私は〇〇(氏名)を私の子として認知します」といった文言を入れることで、法的に認知が成立します。
また、認知手続きを遺言者が行えないため、遺言執行者を指定することが必要です。遺言執行者は、遺言に基づいて非嫡出子の認知手続きを行い、父親の意思を実現する責任を持ちます。遺言執行者には、行政書士などの専門家を指定するのが望ましいです。これにより、遺言の執行が確実に行われ、遺言無効のリスクも避けられます。
遺言書の形式|自筆証書遺言vs公正証書遺言
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。認知を行う遺言書を作成する場合、それぞれの形式の特徴を理解しておく必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きで作成する遺言書です。手軽に作成できる反面、法律的な要件を満たさない場合には無効になるリスクがあります。また、保管方法にも注意が必要です。遺言書が紛失したり、改ざんされたりするリスクもあるため、信頼できる人に保管してもらうか、法務局の「遺言書保管制度」を利用することが推奨されます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、法的に最も強い効力を持つ遺言書です。遺言者が口頭で意思を伝え、公証人が書面に起こす形式ですので、法律的に有効な内容が確保され、紛失や改ざんのリスクも少ないです。非嫡出子の認知に関しても、確実に意思を反映した遺言書を作成する場合、公正証書遺言が最適です。
行政書士に依頼する場合の流れと費用
遺言書の作成や非嫡出子の認知に関して不安がある場合、行政書士に依頼するのが安全です。行政書士は遺言書の作成から、遺言執行者として認知手続きを行うまで、全面的にサポートしてくれます。
費用の目安として、自筆証書遺言の作成サポートで数万円、公正証書遺言の作成サポートでは10万円前後が一般的です。特に複雑な家族構成や財産分与が絡む場合には、専門家に依頼することでトラブルを未然に防ぐことができます。
認知が必要な場合と不要な場合

すべての子供に対して認知手続きが必要というわけではありません。法律上の婚姻関係の有無によって、認知の必要性が変わってきます。この章では、認知が必要なケースと不要なケースの違いについて、法律の視点から整理してお伝えします。
法律上の婚姻関係にない場合の認知の必要性
法律上の婚姻関係がない場合、父親が認知をしない限り、子供は法律上の親子関係が認められません。事実婚や内縁関係にあるカップルの間に生まれた子供は、非嫡出子となり、父親との親子関係を証明するために認知が必要です。
認知がなされない限り、非嫡出子は父親の相続人になれず、父親が遺産を残す場合も法的に守られることはありません。父親が遺産を分け与えたいと考えている場合には、必ず認知手続きを行う必要があります。
母親との親子関係は自動的に成立
母親と子供の間の親子関係は、出産という事実によって自動的に認められます。したがって、母親が認知を行う必要はありません。しかし、父親との間に婚姻関係がない場合は、認知手続きを通じて父子関係を法的に確立する必要があります。
広告
認知の種類と手続き|生前認知と死後認知

認知には、生前に行う方法と、遺言による死後の認知があります。どちらの方法を選ぶかによって、必要な手続きや子供への影響が異なります。この章では、それぞれの認知方法の特徴や流れを比較しながら、どちらが適しているのかを判断するための材料を提供します。
生前認知の手続きと方法
生前認知は、父親が生きている間に行う認知手続きで、市区町村役場に認知届を提出することで行います。手続き自体は比較的シンプルです。認知は、胎児であっても母親の同意があれば行うことが可能です。
また、認知が行われると、子供は法律上の父子関係が成立し、戸籍にもその事実が記載されます。これにより、子供は父親の相続権を持つことになります。
死後認知とは?|遺言で認知を行う場合の手順
死後認知は、父親が生前に認知を行わず、死後に遺言書を通じて認知が成立するケースを指します。
遺言で非嫡出子を認知する際は、遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行う必要があります。
認知された非嫡出子は、父親の相続人として法的に認められ、他の相続人と同等の権利を持つことになります。法改正により、非嫡出子の相続分も嫡出子と同等とされるため、遺言で認知を行うことで、平等な相続が確保されます。
認知に関連する法的手続き
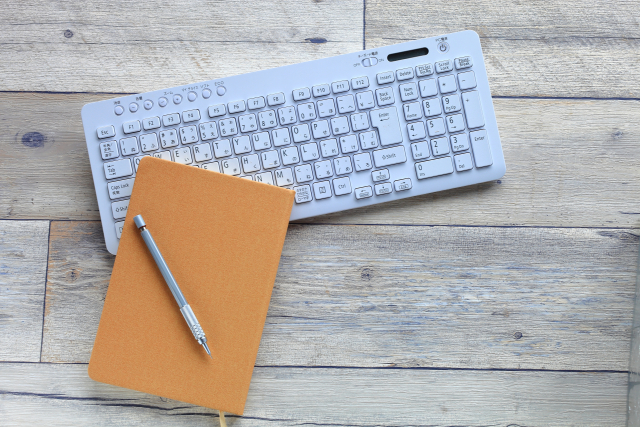
認知が成立すると、その子供は法律上の相続人としての権利を持つことになりますが、それに伴って考慮すべき法的な問題も生じます。ここでは、遺留分などの相続に関する基本的なルールや注意点について、認知後の対応として知っておきたいポイントをまとめます。
遺留分と相続|認知による相続分の確保
遺言で非嫡出子を認知する場合、認知された子供は相続人としての権利を持ちますが、他の相続人の遺留分に配慮した遺産分割が必要です。遺留分とは、遺言者が遺産を自由に分配する権利に一定の制約を加える制度で、遺留分を侵害するとトラブルが生じる可能性があります。
広告
まとめ
非嫡出子の認知は、子供の権利を守るだけでなく、家族間の相続トラブルを未然に防ぐためにも非常に重要な手続きです。この記事でご紹介したポイントを踏まえて、適切な準備を進めていくことが大切です。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。





