遺言書は、自分の死後に財産や権利をどう処分するかを法的に定め、残された家族や相続人に迷惑をかけないために作成する重要な文書です。しかし、遺言書でできることには限界があり、全ての希望を叶えるわけではありません。例えば、葬儀の手配や死後の各種手続きを遺言書に記載しても、法的拘束力はありません。
こうした事務的な手続きを含め、死後の手続きを確実に任せたい場合に役立つのが「死後事務委任契約」です。本記事では、遺言で実現できることとできないこと、そして死後事務委任契約の活用法について詳しく解説します。遺言書作成を考えている方や、終活を進めたい方にとって、役立つ情報をご提供します。
遺言書の基本とは?遺言書作成のメリットと重要性

遺言書は、あなたが亡くなった後に財産をどのように分けるかを定めるための大切な文書です。相続を円滑に進め、家族や親族に無用な争いを避けるために、遺言書を作成することの重要性は計り知れません。ここでは、遺言書の基本的な役割や作成するメリットを詳しく解説します。
遺言書とは?法的に効力を持つ文書の役割
遺言書は、法的効力を持ち、遺言者が亡くなった後、財産や権利の分配を明確に指示するための書類です。遺言書がない場合、相続は民法の規定に基づいて法定相続人の間で分配されます。しかし、遺言書があれば、遺言者の意志を優先して財産分配を行うことが可能になります。
遺言書を作成することで、財産分配に関して家族や相続人の間でトラブルを回避し、遺言者の希望通りに遺産を分割することができます。特に、家族構成が複雑な場合や、特定の相続人に多くの財産を残したい場合には、遺言書が必須です。
遺言書の種類
遺言書には3つの種類があります。それぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。
公正証書遺言
公証人役場で公証人が作成し、法的な問題が生じにくい形式の遺言書です。行政書士や弁護士といった専門家がサポートすることも多く、確実性が高いのが特徴です。作成後は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のリスクがありません。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する遺言書で、費用をかけずに作成できる反面、法律の不備や誤記があると無効になるリスクがあります。2020年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や印刷が認められていますが、それ以外はすべて手書きでなければなりません。保管については、法務局に預ける制度も新たに設けられました。
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証人役場に預ける形式の遺言書です。遺言の内容は自分で作成しますが、署名と捺印を公証人の前で行い、公証役場に保管されます。しかし、内容の正当性は保証されないため、あまり利用されない形式です。
遺言書作成のメリット
遺言書の作成には、次のような大きなメリットがあります。
相続トラブルの回避
遺言書がないと、法定相続に従った分配が行われますが、相続人間で意見が対立することも多々あります。遺言書があれば、財産分配に関する争いを避けることができます。
希望に沿った財産分配
例えば、特定の人に多くの財産を残したい場合や、遺産を寄付したい場合など、遺言書を通じて自分の意志を実現できます。
特定の資産を指定できる
家や土地などの特定の財産を誰に相続させるか、細かく指定することが可能です。
これにより、相続人の間で無用な争いが避けられ、遺言者の意志が正確に反映されるため、遺族にとっても大きなメリットがあります。
広告
遺言で実現できることとできないことを徹底解説

遺言書は、あなたの死後の希望を反映させるために役立ちますが、すべての希望を叶えるわけではありません。財産の分配に関する事項は遺言書で実現できますが、葬儀の手配や日常的な手続きなどは対応できないのが現実です。このセクションでは、遺言書で実現可能なことと、実現できないことを明確に解説します。
広告
遺言書で実現できること 財産分与や相続人の指定
遺言書では、主に財産に関する事項を法的に指定できます。具体的には以下のようなことが可能です。
相続人の指定
法定相続人の中から、特定の人に多くの財産を残すことが可能です。例えば、配偶者にすべての財産を残すといった場合、遺言書で明確に指定できます。
遺贈の指示
相続人以外の人や団体に財産を残す「遺贈」も遺言書を通じて行うことができます。例えば、友人や慈善団体に寄付することも可能です。
特定の財産の分割方法の指定
不動産や車、貴金属など、特定の財産を誰に相続させるかを指定できます。
相続人の廃除
特定の相続人を相続から除外する「廃除」も遺言書に記載できます。例えば、家庭内でトラブルがあった場合や、相続をさせたくない理由がある場合に、法的に相続人から外すことができます。
遺言書でできないこと 葬儀や死後の手続きに関する指示
遺言書でできることは財産の分配に限られ、次のような事項については遺言書では法的拘束力がありません。
葬儀の方法や場所の指定
葬儀の形式や火葬の手配などについては、遺言書に記載しても法的効力がなく、あくまで「希望」として扱われます。
遺品整理や不要品の処分
これらは相続人や遺族が対応するべき事務手続きとなるため、遺言書では指示できません。
契約の解約手続き
銀行口座の解約やクレジットカードの停止、携帯電話や電気・ガスの解約手続きも遺言書では対応できません。
役所手続き
死亡届の提出など、死後に役所で行う事務手続きについても遺言書では法的拘束力がありません。
このため、これらの手続きや希望を確実に実行するためには、別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。
遺言執行者の選任と役割 法的に必要な手続きの実行者
遺言書には「遺言執行者」を指定することが可能です。遺言執行者とは、遺言書の内容を法的に実行する責任者で、遺言者が亡くなった後、財産の分配や相続手続きを行います。遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所が選任することもあります。
ただし、遺言執行者が行えるのは財産の分配や相続手続きまでであり、葬儀の手配や死後の事務手続きについては含まれません。これを補完するのが「死後事務委任契約」です。
広告
死後事務委任契約とは?
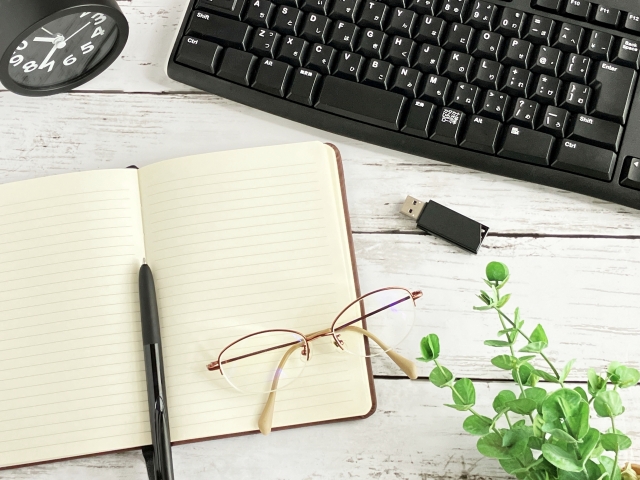
遺言書では、死後に必要な事務的手続きを全て指定することはできません。そこで活躍するのが「死後事務委任契約」です。この契約を結ぶことで、葬儀の手配や不要品の整理、契約の解約手続きなど、遺言書ではカバーできない部分を任せることができます。このセクションでは、死後事務委任契約がどのような役割を果たすのか、そしてどんな手続きを委任できるのかを詳しくご説明します。
死後事務委任契約とは?その役割と法的効力
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後の葬儀や各種手続きを、事前に指定した受任者に任せる契約です。受任者は、遺言者の死後に法的な拘束力を持ってこれらの手続きを実行します。具体的な内容は契約時に細かく決めることができ、遺言書でできない手続きを確実に行わせることができます。
遺言書と死後事務委任契約の違いと補完関係
遺言書は財産分配に関する法的効力を持つものですが、死後事務委任契約は死後の事務手続きに法的効力を持たせるものです。例えば、以下のように両者を補完的に利用できます。
遺言書
相続に関する事項(財産分配、相続人の指定など)
死後事務委任契約
葬儀、火葬、遺品整理、契約の解約などの事務手続き
死後事務委任契約で解決できる手続き一覧
死後事務委任契約で委任できる具体的な手続きには、以下のようなものがあります。
葬儀の手配
葬儀の形式や会場、参列者への連絡を行う
火葬や納骨手続き
役所への届出や許可取得、火葬場の手配
遺品整理
不要な品の処分や形見分け
各種契約の解約
銀行口座やクレジットカード、携帯電話、光熱費の解約
役所手続き
死亡届の提出や住民票の抹消など
これらの手続きは、遺族が行うには非常に労力がかかるため、死後事務委任契約によって専門家に任せることで安心して終活を進めることができます。
広告
行政書士に依頼するメリット

遺言書や死後事務委任契約を作成する際、専門家である行政書士に依頼することには大きなメリットがあります。正確で法的に有効な手続きを進めるためには、経験豊富な行政書士のサポートが欠かせません。ここでは、行政書士に依頼するメリットと、依頼時に注意すべきポイントについて詳しく紹介します。
遺言書と死後事務委任契約を同時に依頼するメリット
行政書士に遺言書と死後事務委任契約の両方を依頼することで、スムーズな終活が可能になります。遺言書では法的に財産の分配を明確にし、死後事務委任契約で死後の煩雑な手続きを専門家に任せることで、家族や親族の負担を減らすことができます。また、行政書士に依頼することで、手続きに関する法的な不備やミスが防げ、遺言者の希望が確実に実現されます。
広告
まとめ
遺言書と死後事務委任契約を併用することで、財産の分配から死後の手続きまでをスムーズに進め、家族に余計な負担をかけずに済む終活が可能になります。行政書士に相談しながら、自分の希望に沿った未来設計をしていくことをお勧めします。
家族のためにも、そして自分自身のためにも、遺言書と死後事務委任契約を活用して、安心して終活を進めていきましょう。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。






