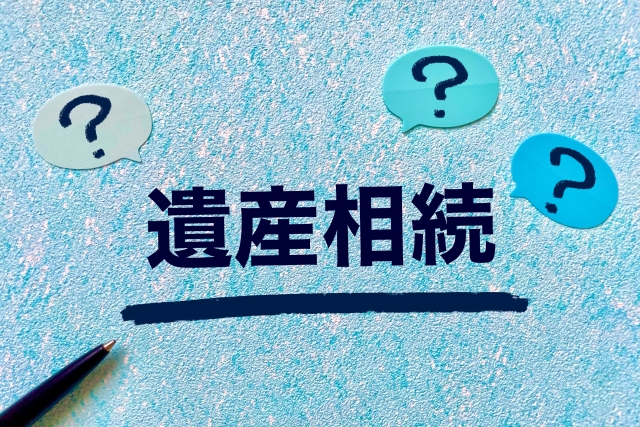遺言書の作成は、相続人や遺贈人への意思表示により、相続や遺贈の内容が変わる可能性がある重要な手続きです。「〇〇を相続させる」は相続人への相続分の指定を、「〇〇を遺贈する」は相続人以外への財産贈与を意味します。遺言書を書く際には、自分の意思を反映した表現を選ぶことが大切です。この記事では、遺言書の表現の違いと、遺言書作成時の注意点について詳しく説明します。遺言書の作成に関する知識を深め、適切な遺言を残すためのガイドとしてご活用してください。
相続させる遺言とは?その定義と基本を解説

特定財産承継遺言とは、遺産の一部を特定の相続人に指定して承継させる遺言のことです。具体的には、「この土地を長男の○○に相続させる」といった形で、特定の財産を特定の相続人に指定します。以前は「相続させる旨の遺言」と呼ばれていましたが、民法改正により、「特定財産承継遺言」という名称に変更されました。
(特定財産に関する遺言の執行)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第千十四条
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
相続させる遺言の特徴メリットとデメリットを徹底分析

相続させる遺言は、特定の財産を特定の相続人に指定し、「相続させる」と記載する遺言のことを指します。この遺言は、遺言者がどのような効力を望んでいたのか必ずしも明らかでなく、効力の判断が難しいこともあります。しかし、「相続させる」との遺言は、財産を譲り渡す相手方が「法定相続人」に限られています。
広告
相続させる遺言のメリットとデメリット
特定財産承継遺言の最大の利点は、遺産分割協議を経ずに財産の名義変更が可能であることです。例えば、特定財産承継遺言がある場合、長男は土地や建物の名義を自分に変更するために、他の相続人の協力を必要としません。同様に、長女が銀行の預金を解約したり、証券会社の有価証券を自分の口座に移したりする際に、長男の同意は必要ありません。
一方、特定財産承継遺言がない場合、原則として遺産分割協議を経なければ名義変更などの手続きはできません。つまり、特定財産承継遺言がない場合、財産の名義変更や解約等を行うには、相続人全員の協議が必要となります。
特定財産承継遺言(相続させる遺言)のメリットとデメリット
相続させる遺言のメリットは以下のとおりです。
- 相続発生時に遺産分割協議や家庭裁判所の審判を経ずに、受益相続人が遺産を確定的に取得できる。
- 不動産の所有権移転登記を受益相続人が単独で申請できる。
- 農地や借地権などの特殊な財産についても、許可や承諾を要しない場合がある。
相続させる遺言のデメリットは以下のとおりです。
- 相続人以外の者に財産を与えることができない。
- 受益相続人が遺言者より先に死亡した場合、その相続人に財産が引き継がれない。
- 遺留分減殺(遺留分侵害額請求)の順序や負担付の場合の法律関係など、一部の問題点については判例や学説の見解が分かれる。
広告
遺贈する遺言とは?基本から応用まで

「遺贈」とは、遺言によって特定の相手に財産を引き継がせることを指します。遺贈の相手は法定相続人でも良いですし、法定相続人でない他人でも構いません。また、遺贈の相手は特定の個人だけでなく、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの団体や法人に設定することも可能です。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
- 「包括遺贈」は、遺産の内容を特定せずに全部、あるいは遺産全体の何割、何分の何というように割合によって与える遺贈を指します。
- 「特定遺贈」は、あらかじめ遺産のうちの特定のものを指定して、与える遺贈のことです。
遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。受遺者は被相続人の相続開始時に生存している人でないといけません。
ただし、胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなされるため受遺能力があります。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じません。
広告
遺贈する遺言の特徴をまとめました
遺贈の最大の特徴は、法律上、相続人でない人にも財産を遺せるという点です。以下に、遺贈する遺言の主な特徴をまとめてみました。
- 遺贈の対象:遺贈では、法定相続人でない親族や第三者に対して、財産を取得する権利を与えることができます。遺贈の相手を、法人とすることも可能です。
- 遺贈の必要性:遺贈は、遺言によって行う必要があります。遺言は、年齢が15歳に達しなければ行うことができませんので、遺贈もまた15歳を迎えた人しかできないことになります。
- 遺贈と相続の違い:遺贈と相続の違いは、遺贈では法定相続人以外の相手に財産を取得させることが可能であること、遺贈は遺言を行うことが必要であること、相続登記の申請者が違うこと、不動産取得税の扱いが違うこと、遺贈には代襲相続がないことなどが挙げられます。
- 遺贈の受け取り:遺贈によって財産を取得する人のことを「受遺者」といいます。受遺者は、遺贈を放棄することもできます。
遺贈する遺言のメリットとデメリット
遺贈する遺言のメリットは以下のとおりです。
- 相続人以外の者にも財産を与えることができる。
- 受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その相続人に財産が引き継がれる。
- 個別の遺贈ごとに放棄することができる。
遺贈する遺言のデメリットは以下のとおりです。
- 不動産の所有権移転登記を受遺者と他の相続人全員との共同申請が必要となる。登記をしなければ第三者に対して所有権を取得したことを対抗できない。
- 農地や借地権などの特殊な財産については、許可や承諾を要する場合がある。
法律で見る相続と遺贈の違い

「相続させる遺言」と「遺贈する遺言」は、どちらも遺言者が死亡した場合に特定の者が財産を取得することになるという意味では同じですが、その適用範囲と法的効果に違いがあります。
「相続させる遺言」は、財産を譲り渡す相手方が「法定相続人」に限られています。つまり、ある特定の財産を特定の相続人のみに承継させたい時に適用されます。また、「相続させる遺言」の場合、不動産を相続した場合でも、他の相続人の協力なしに所有権移転登記を単独で行うことができますし、登記しなくてもその権利を第三者に対抗することができます。
一方、「遺贈する遺言」は、遺言によって財産を無償で譲り渡す意思表示のことを指します。法定相続人以外の第三者にも財産を渡すことができます。しかし、「遺贈」の場合、所有権移転登記は単独ではできず、他の相続人の協力が必要です。
したがって、特定の財産を承継させたい人が法定相続人である場合は、「遺贈」ではなく「相続させる遺言」にするべきでしょう。これにより、他の相続人の協力なしに所有権移転登記を行うことができます。
広告
相続か遺贈か?遺言を選ぶための決定要因
遺贈と相続の主な違いは、「財産を受け取る権利がある人」と「税金の種類や税率」です。遺贈は遺言によって特定の相手に財産を引き継がせることで、一般的には遺贈の相手は「相続人以外の人物や団体」となりますが、遺贈の相手を相続人とすることも可能です。
遺贈を選ぶべき状況は以下のような場合です。
- 法定相続人以外に財産を渡したい場合:遺贈の相手は相続人以外の第三者でも団体や施設でも構いません。したがって、法定相続人以外の人物や団体に財産を譲りたい場合には「遺贈」を使います。
- 特定の財産を特定の人に渡したい場合:遺贈は特定の財産を特定の人に譲ることができます。したがって、特定の財産を特定の人に譲りたい場合には「遺贈」を選ぶことができます。
ただし、遺贈には注意点もあります。遺贈と相続では、手続きや適用される税金が異なってくるため、財産を残したい相手のことを考えるなら、さらに詳しく違いを理解しておく必要があります。具体的には、遺贈の場合、相続人全員+受遺者と共同で手続きする必要があり、必要書類もたくさん集めなければなりません。また、遺贈により相続人以外の方が不動産を取得する場合、不動産取得税がかかったり、通常の相続における登録免許税よりも高くなったりと、一般的には課税の負担が大きくなる可能性があります。
他にも不動産登記などの手続き上の違いもあります。相続財産に不動産がある場合に、最終的に法務局で、不動産の登記を行いますが、「〇〇を相続させる」「〇〇を遺贈する」で手続きが変わります。遺言書が「〇〇を相続させる」という文言の場合以前は、登記がなくても相続人は第三者に対抗(権利を主張できました)ですが、民法の改正で、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなれば、第三者に対抗することができないとされました。
さらに、農地などが相続財産にある場合に、「〇〇を相続させる」文言であれば、相続による所有権移転ができますが、遺贈する遺言の場合は、改めて農業委員会の許可が必要となり手続き上面倒なことがあります。
相続財産に借地権・借家権がある場合も、賃貸人の承諾は不要ですが、遺贈する遺言は、包括遺贈と特定遺贈で結論がことなります。包括遺贈の場合は、承諾は不要ですが、特定遺贈の場合は必要となります。適切な選択をするためには、これらの違いを理解し、専門家に相談することが重要です。
まとめ
遺言とは、生前の意思を明確にし、死後の財産の分配を決定する法的手段です。相続させる遺言と遺贈する遺言は、その方法と目的により異なります。
相続させる遺言は、遺言者が死亡した後、特定の人物に財産を相続させるためのものです。
一方、遺贈する遺言は、遺言者が生前に特定の人物に財産を贈与するためのものです。
相続させる遺言と遺贈する遺言の選択は、遺言者の状況と目的によります。相続させる遺言は、遺言者が死後の財産の分配を決めたい場合に適しています。一方、遺贈する遺言は、遺言者が相続人以外の人に財産を渡したい場合に適しています。
遺言の作成は、専門的な知識や手続きが必要です。遺言の作成をサポートは当事務所で行っております。遺言の作成に関するご相談やお問い合わせは、[こちら]からお願いします。遺言の作成に関する詳しい情報は、[こちら]をご覧ください。
遺言を作成することは、あなたの大切な人や財産を守ることにつながります。遺言の作成をお考えの方は、是非当事務所にご連絡ください。あなたのニーズに合わせた最適な遺言書の作成をお手伝いします。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。