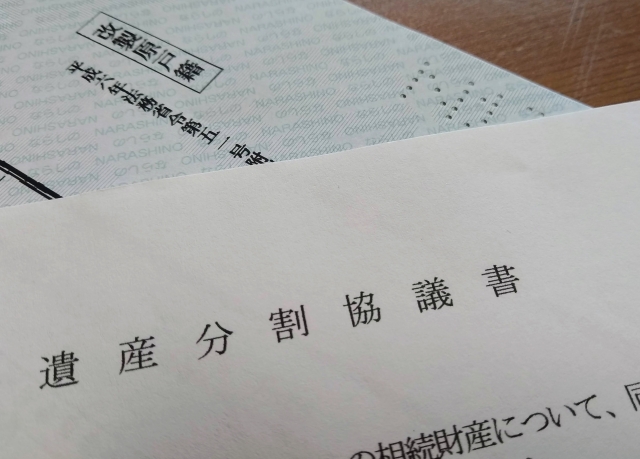相続が発生すると、相続人を調査し相続財産を調査、遺言書の有無を確認後に相続人全員で話し合いをして、相続財産を誰に相続させるかを決めます。
遺産分割協議の内容を、書面にして残したものが遺産分割協議書です。
今回の記事では、遺産分割協議書作成するには全員が集まる必要があるかや、遺産分割証明書とは何か、遺産分割協議をする前に勝手に財産を処分した場合について解説していきたいと思います。
遺産分割協議書作成の流れと手続き

相続が発生したら、相続人全員で被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を誰が相続するかの話し合いをします。
遺産分割協議の内容は必ずしも書面にする必要はありませんが、その後に不動産の名義変更、預貯金の払戻し等を行う際に、書面で証明する必要がありますし、後で何をどのように合意したかは口頭だけでは、後からそんな話でなかったと、揉める事になるかもしれません。そのため、合意した内容を後から証明できるように遺産分割協議書を作成する必要があります。
広告
遺産分割協議書の書き方添付する書類や注意する点
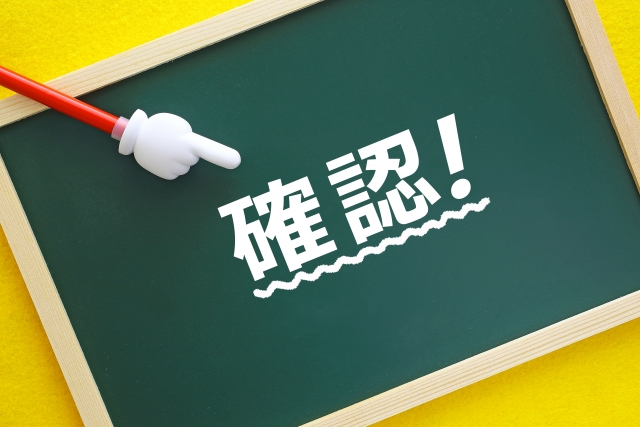
遺産分割協議書は、どの相続人にどんな財産を承継させるのかを記載した書類です。
遺産分割協議書には、特定した相続人や、誰にどんな財産を、どれだけ相続させるのか記載します。
署名捺印について
署名捺印をする際には、住所と氏名は添付する印鑑証明書に記載されている通り署名するようにしてください。
遺産分割協議書には、相続人本人が確かに押印したことを証明するため、実務上は印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書には直接は関係ありませんが、遺産分割協議の内容に預貯金がある場合には、あとから、預貯金を払戻すことになると思いますので、金融機関に確認して事前に必要書類に押印をしてもらえば、手間が省け、もう一度相続人が捺印する必要もなくなります。
不動産がある場合の物件の記載方法
遺産の中に不動産がある場合は、物件の所在地を住所で記載しないで、必ず法務局で取得した不動産の登記簿謄本通り記載してください。
相続分のない相続人がいる場合
相続分がなくてもよいという相続人がいる場合は、それらの相続人から特定の相続人に相続持分の譲渡書を出してもらい、残る相続人で遺産分割協議書を作ることもできます。
遺産分割協議は相続人全員が必ず集まらなくてはならないのか

遺産分割協議は、共同相続人全員が合意することによって成立します。
基本的には相続人全員が集まり話し合うことが望ましいのですが、相続人が遠方に住んでいたり、高齢の方が相続人にいて、移動が難しい場合など、相続人全員が一堂に会するには、現実的に厳しい時があります。
そういった場合は遺産分割協議証明書を作成することにより、必ずしも全員が一堂に介して話し合いをする必要はありません。
遺産分割の内容が確定しており、その内容を各相続人全員に提示することにより、遺産分割協議を行うことができます。(相続人の署名捺印と印鑑証明書は必要です)
遺産分割協議書を複数枚に分けることはできるか
遺産分割協議書に関しては、1枚の書類に持ち回りで押印してもらうこともできますが、相続人が多いときや、相続人が遠方にいる場合は、持ち回りで作成することは困難だと思います。
そのため、遺産分割協議証明書を相続人全員分作成して、遺産分割が相続人全員で行われた事を証明することも可能です。
不動産の名義変更を行う際には、この遺産分割協議証明書を用いて手続きを行うことになります。
広告
遺産分割協議をする前に相続人が勝手に遺産を使ったらどうなるのか

基本的に、被相続人(亡くなった方)が有していた財産は、相続人を確定して、相続財産を調査した後に遺産分割協議を行い、誰に相続財産を相続させるか決めることになります。
ただ、一部の相続人が他の相続人の同意を得ないで財産を処分してしますことが、現実としてあります。
例えば、各金融機関の預貯金を一部の相続人が被相続人が亡くなってから、口座が凍結する前に駆け込みで、預貯金を引き出してしまうケースが考えられます。
広告
遺産を勝手に処分されたときにできること
民法改正前の実務では、被相続人の遺産を勝手に処分した相続人がいる場合に、相続人全員の合意がないときは、勝手に処分した財産を除いて遺産分割を行うこととされていました。
つまり、勝手に預貯金を引き出した相続人が、引き出さなかった場合と比較して得をしてしまうということになってしまいます。
今までの取り扱いでは、先に引き出した一部の相続人が、結果として得してしまうことになってしまいます。
なぜこのような結果になってしまうのでしょうか。
考え方として、遺産分割の手続きは、相続開始時に存在して、かつ、遺産分割時(遺産分割協議をして話がまとまった後)に存在する財産を分配する手続きであると考えられていました。
つまり、一部の相続人が勝手に預貯金の払戻しをうけたり、遺産を隠匿したりしても、その処分した財産は遺産分割協議をするときには、存在していない財産とされるために、遺産分割の対象でないと判断されています。
一般の方は、疑問に思う考えかと思いますが、法律の考え方だとこうなってしまい、真っ当なことをする相続人が損をしてしまいます。
ただ以前も全く救済の方法がなかったわけではなく、遺産を処分した相続人に対して、他の相続人が不法行為や不当利得に基づく請求をして、裁判で解決すべきであるとされていました。
改正民法の考え方
民法改正がされた際に上記の内容が変更となりました。
いくつか要件がありますが、変更点として、相続開始後、遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、共同相続人の全員がその処分された財産を遺産分割の対象とすることに同意すれば、その財産を含めて遺産分割することができ、その処分した相続人の同意を必要としないで、他の共同相続人が処分された財産を遺産分割の対象とすることを同意すれば、その処分財産を含めて遺産分割することができます。
民法改正で、公平な遺産分割ができるようになりましたが、あくまで相続人が処分した場合ですので第三者が引き出した可能性がある場合は、裁判所での手続きが必要となります。
広告
第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
民法 – e-Gov法令検索より引用
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
まとめ
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、遠方に相続人がいる場合や、相続人が高齢な場合は相続人全員が集まれない事もあります。
そういった場合は、遺産分割協議証明書を作成することにより、相続手続きを進める事ができます。
遺産分割協議書を作成する前に遺産を処分した相続人に対しては、以前の民法では、勝手に処分された財産は裁判所で争うしかありませんでしたが、民法改正により、裁判を経ることなく、解決できる選択肢も増えました。
今回は遺産分割協議書について解説をしましたが、遺産分割協議書を作成したのち、作成した遺産分割協議書を金融機関や役所の手続きで使用することになりますので、とても大事な書類となります。
法律の知識がないと、作成に困ることもございますので、書類作成の場合は当事務所にご相談ください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。