相続手続きや遺産分割は、相続人にとって大きな負担となることが多いです。特に、遺産に不動産や株式などの換金しにくい資産が含まれている場合、その分割方法を巡って争いが生じやすくなります。そんな中で「清算型の遺言書」や「清算型遺産分割協議書」が有効な手段として活用されています。
この記事では、「清算型の遺言書・遺産分割協議書とは何か」という基本から、具体的な作成方法やメリット・デメリット、不動産を換金して分配する手続きまで詳しく解説します。
広告
遺言書の種類と清算型遺言書の特徴

相続の準備を進める上で、まず理解しておきたいのが「遺言書」の種類とそれぞれの特徴です。特に、財産を換金して分配する「清算型遺言書」は、一般的な遺言書とは異なる視点での設計が求められます。ここでは、遺言書の基本的な形式を押さえた上で、清算型遺言書の特徴と適したケースについて詳しく解説します。
遺言書の種類とは?自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の違い
遺言書には、主に3つの形式が存在します。それぞれの形式は、手続きや証明力に違いがあります。
自筆証書遺言
遺言者が自分で全て手書きする形式です。2019年の法改正により財産目録部分は自筆でなくてもよくなりましたが、本文は自筆が原則です。費用はかかりませんが、形式に不備があると無効になるリスクが高いです。また、遺言書が自宅などで保管されるため、紛失や改ざんのリスクもあります。
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する形式です。遺言者が口述した内容を公証人が書面にし、法律に基づく厳格な手続きの下で作成されます。保管も公証役場で行われるため、紛失や改ざんのリスクはありません。作成には公証役場への手数料が必要ですが、内容が法的に確実であるため、相続トラブルを避けるためには最も安心な形式です。
秘密証書遺言
遺言書の内容を誰にも知られずに作成する形式です。封印して公証人がその封印事実を証明します。ただし、公証人は内容を確認しないため、形式に不備があると無効になるリスクが残ります。
清算型の遺言書とは?財産を換金して相続人に分配する方法
清算型の遺言書とは、遺言者が持っている財産を、相続発生後に換金して、その現金を相続人に分配する内容を定めた遺言書です。特に不動産や株式などの資産がある場合、それらを相続人に現物で渡すのではなく、一度売却して現金化することで、全員に公平に分けることが可能になります。
清算型遺言書が適しているケース
- 不動産や株式など換金性の低い資産が多い場合
不動産や株式などの資産は、相続人間で均等に分けるのが難しいため、換金して現金を分けた方が公平です。 - 相続人間のトラブルを避けたい場合
相続財産を現物で分ける場合、相続人間で分割方法について争いが起きることが少なくありません。現金で分けることで、争いを防ぐことができます。 - 相続人が不動産を使う予定がない場合
相続人が全員、相続した不動産に住む予定がない場合、売却して現金にした方が後々の管理や維持費の負担も軽減されます。
広告
清算型の遺産分割協議書とは?不動産を換金する具体的な方法

遺言書がない場合や、遺言の内容にすべての財産が含まれていない場合、相続人同士の話し合いによって分割方法を決める必要があります。特に不動産などを換金して分ける「清算型」のアプローチは、トラブルを防ぐ有効な手段となります。この章では、清算型遺産分割協議書の基本的な仕組みと、不動産を現金化して分配する具体的な手続きについて解説します。
遺産分割協議書の役割と清算型の仕組み
遺産分割協議書とは、遺言書がない場合や、遺言書の内容に沿っていない財産の分割について、相続人全員が話し合って合意した内容を文書にまとめたものです。特に不動産を含む相続の場合、その取り扱いについては協議が難航することが多く、全員が納得できる形で分割するために清算型の遺産分割協議が行われることが多いです。
清算型の遺産分割協議書では、相続財産の一部または全部を売却し、その売却代金を相続人に分配する旨が記載されます。これにより、相続人間で公平な分配が行われ、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。
不動産を換金して分配する具体的な手順|売却の流れと登記手続き
不動産を換金して相続人に分配する際には、以下の手順を踏んで手続きを進めます。
- 相続登記の手続き
最初に、不動産の名義を亡くなった人から相続人に移す手続き、いわゆる相続登記を行います。この手続きが完了して初めて、不動産を売却することが可能になります。相続登記には、法務局で登記簿謄本を取得し、登記内容を確認してから必要な書類を提出します。 - 不動産の売却手続き
相続登記が完了したら、不動産を売却する手続きに入ります。売却先を探すためには、不動産会社を通じて買い手を見つけることが一般的です。遺言執行者がいれば、執行者が売却手続きを進めますが、いない場合は相続人全員の協力が必要です。 - 売却代金の分配
不動産を売却した後、その代金を清算型遺言書や遺産分割協議書に基づいて分配します。この際、税務処理についても注意が必要です。売却によって得た利益には譲渡所得税がかかることがあり、その計算と支払いを行う必要があります。
広告
清算型の遺産分割協議書を作成する際の手順
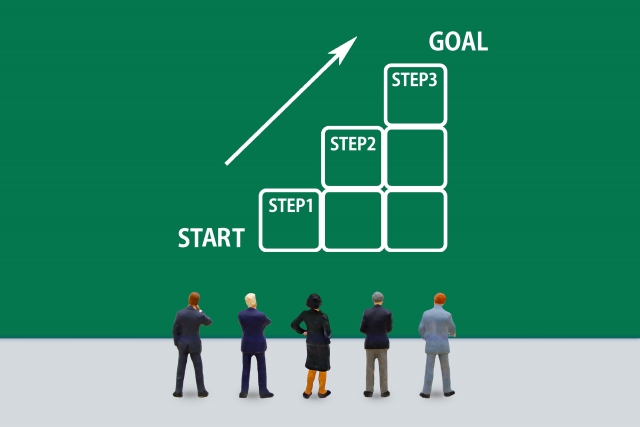
清算型の遺産分割協議書を実際に作成するには、相続人全員の同意と、法律的に正確な手続きが欠かせません。売却対象となる財産の特定から、分配方法の決定、書面の完成まで、段階を踏んで進める必要があります。このセクションでは、実務的な視点から、作成の流れや注意点、そして遺言書との違いについて詳しく見ていきます。
遺産分割協議書の作成手順|財産を売却して分配する場合の注意点
清算型の遺産分割協議書を作成するためには、まず相続人全員が同意することが前提です。その上で、以下の手順で作成します。
- 売却対象となる不動産や財産の特定
まず、遺産分割協議の対象となる不動産や財産を明確にします。不動産の場合、登記簿謄本に記載されている情報を基に特定し、その詳細を協議書に記載します。 - 売却後の分配方法を決定
売却した後、どのように代金を分配するかについて協議します。法定相続分に基づく場合が多いですが、相続人間で合意すれば異なる割合で分けることも可能です。これを協議書に明記します。 - 相続人全員の署名と押印
協議書が完成したら、相続人全員の署名と押印が必要です。全員の同意を得た協議書でなければ、効力がありません。
清算型遺産分割協議書と遺言書の違い|手続きの流れと法律的な観点
遺言書と遺産分割協議書には、いくつかの大きな違いがあります。
遺言書は遺言者が一方的に財産の分配方法を決めるもので、相続人は基本的にその指示に従います。一方で、遺産分割協議書は、相続人全員の話し合いによって合意を得た結果をまとめた文書です。
遺言書の場合は、遺言執行者が指定されていれば、その者が主導して手続きを進めますが、遺産分割協議書の場合、相続人全員が手続きを進める必要があり、意見の対立が起こりやすいのが特徴です。
清算型遺言書・遺産分割協議書を活用するメリットと注意点

公平な相続を実現するために有効な清算型の方法ですが、もちろん万能ではありません。実際に活用する際には、具体的なメリットとともに、税務処理や手続き上の注意点も理解しておくことが大切です。この章では、清算型遺言書や協議書を使う利点と、注意すべきポイントについて、事例を交えながら分かりやすく解説します。
清算型の遺言書を利用するメリット|公平な財産分配と相続トラブル回避
清算型の遺言書や遺産分割協議書の最大のメリットは、公平な分配が可能であり、相続トラブルを防げる点です。不動産を現物で相続すると、後にその管理や維持費などが問題になることが多く、相続人間での対立も生じがちです。しかし、現金での分配であれば、相続人全員に公平に分けることができるため、後々のトラブルを避けられます。
税金や手続きの複雑さに対する注意点|事前の準備と専門家の活用が重要
一方、清算型の遺言書や遺産分割協議書を利用する際には、税金や手続きの複雑さにも注意が必要です。特に、不動産売却による譲渡所得税や相続税についての対応が必要です。売却によって得た利益に対する税金や、相続税の支払い方法については、税理士に相談して適切に対応することが求められます。
広告
清算型遺言書・遺産分割協議書を行政書士に依頼するメリット

清算型遺言書や遺産分割協議書の作成や相続手続きを行政書士に依頼することには、多くのメリットがあります。行政書士は相続に関する法律知識を持ち、手続き全般をスムーズに進めるサポートを行います。また、専門的な助けを得ることができるため、安心して進めることが可能です。
広告
まとめ
清算型の遺言書や遺産分割協議書は、特に不動産など流動性の低い財産が含まれる相続において、有効な解決策です。相続人全員が納得する公平な分配を行い、トラブルを回避するためにも、事前に準備を進めることが大切です。また、行政書士などの専門家に依頼することで、スムーズかつ適切な手続きを行うことができます。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。



