外国人が日本に上陸する際には、上陸許可を取得し、日本に在留するためには、在留許可を取得しなくてはなりません。
在留資格にも就労できるものとできないものがあり、在留資格の種類によって制限があります。
今回の記事では、就労できる教授の在留資格に関して解説していきたいと思います。
外国人が日本で遺言書を作成したい場合はどうすれば良いのか
外国人が大学などで働くには
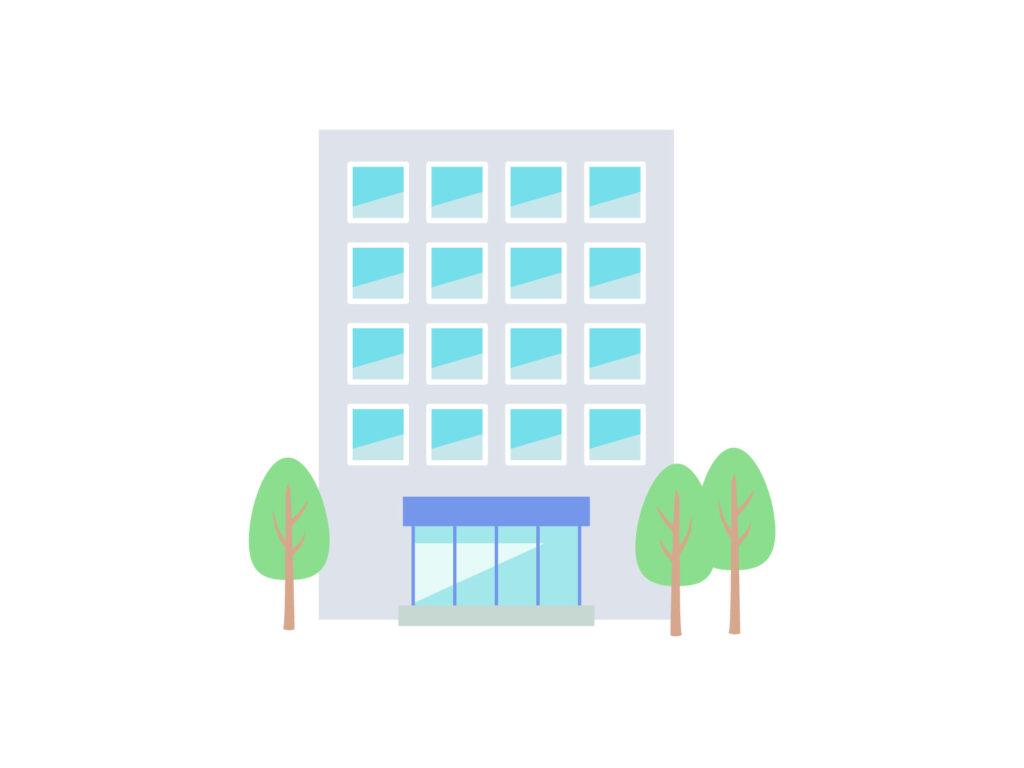
教授の在留資格(就労VISA)は、日本における学術研究および高等教育の向上を目的として、大学教授などを受け入れるために設けられた在留資格です。
教授の在留資格は、学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として研究、研究の指導、または教育をする活動が該当します。
教授の在留資格とは

教授の在留資格は、日本の4年生の大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属の研究所も含まれ、常勤非常勤にかかわらず、実質的にその機関において研究、研究の指導又は教育をする活動に従事するかどうかによって、在留資格の該当性が判断されることになります。
教授の在留資格を取得するためには、日本で安定した生活が送れる十分な収入が必要となります。
民間の会社で講師をしたりする場合など、大学に準ずる機関に該当しない場合には、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することになります。
他にも大学で常勤の職員か、非常勤の職員課でカテゴリー等が変わりますので、ご注意ください。
まとめ
日本の4年生の大学などで、教授、准教授、講師などで仕事をしたい場合には、教授の在留資格を取得する必要があります。
民間会社で外国語の教師で働く場合や大学に準ずる機関に当たらない場合には、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することになります。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。


