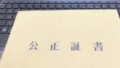遺言書を作成しようと考えている方もいらっしゃると思いますが、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、その中から選択して遺言書を作成します。
遺言書の内容は様々ですが、法律で定められた要件を欠いたものは法的に効力がなく、思いを叶えることができません。
今回の記事では、遺言書を書くにはどうすればよいのか、遺言書の種類について自筆証書や公正証書とは書き方や年齢について解説したいと思います。
遺言を作成することができる年齢

遺言は満15歳になれば誰でも作成することができます。
ただし、遺言書を書くときは、意思能力が必要ですので、認知症などで自分の本当の意思かどうかわからない場合は、遺言をすることができません。
広告
遺言書の種類
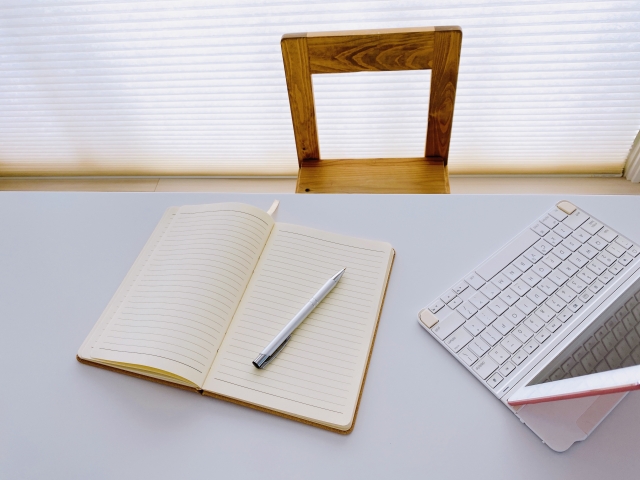
遺言書には大きく自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言の4種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いた遺言の事ですが、全文、日付及び氏名を自書して、押印しないと効力が生じません。(法改正で、財産目録は自筆でなくても大丈夫になりました)
自筆証書遺言を訂正する時は、線を引いて訂正印を押すだけでは、ダメで法律に則ったやり方で訂正をしなくてはなりませんので、書き損じがある場合は面倒ですが、改めて書き直す方が良いかと思います。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。
(自筆証書遺言)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に依頼して作成するものです。公証役場で手続きを行うのですが、自筆証書遺言と違い、本人が自書する必要がなく、ご高齢で自ら遺言を書くことができない方や、体に障害がある方も利用することができます。
公正証書遺言は2人以上の立会いが必要だったり、戸籍、不動産がある場合は、登記簿謄本などの書類が必要になります。家庭裁判所の検認は不要です。
(公正証書遺言)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書に封をしたものを公証人に提出して、自分の遺言だと証明してもらいます。証書に署名をして印を押さなくてはなりませんが、自筆証書遺言と違い、必ず全文自書である必要もありません。(最低でも署名と押印が必要です)
証書を封筒に入れて、封をして、証書に押印した印鑑を使い、遺言者と証人2名とともに封筒に押印して封印し、遺言書を返してもらい遺言者がその遺言書を保管します。家庭裁判所の検認も必要です。
(秘密証書遺言)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
特別方式の遺言
特別方式の遺言は、病気や遭難など緊急の時に使える遺言です。日常生活であまり使われることはないかもしれませんが、緊急時に遺言を残すこともできます。
(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の
証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)
第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)
第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
遺言書を書く際に必要なもの

自筆証書遺言を書く際には、用紙や筆記用具が必要となりますが、用紙や、筆記用具に法律の決まりはあるのでしょうか。
用紙に関しては、紙の大きさやなどに制限はありませんので、A4の用紙でもノート、便箋、チラシの裏でも大丈夫です。
ただし、遺言書は長い年月保管されるものと想定されますので、最低でも、長い期間保管できて、遺言書とわかるようにしなくてはなりません。遺言を書いたのに気付かれないで、捨てられたら意味がありません。
筆記用具に関しても、法律上の規定はないため、ボールペン、万年筆、筆、鉛筆でも大丈夫ですが、鉛筆だと後から相続人が消したり、偽造が容易にできてしまうので、ボールペンなど文字が後から消せないもので記載するようにしてください。
広告
遺言書を書くときに注意すること
法律で遺言書を作成する際に、縦書、横書、文字数などに制限はありませんし、無理に法律用語を書く必要もありません。
内容がわかるように丁寧な字で書くこと、後から相続人が手続きができるように、具体的な財産を誰に承継するのかを記載します。
特定の財産を相続人等に遺贈したい場合は、抽象的に書かないで、具体的にどの財産かわかるように記載します。
遺言書を書く際には、標題に決まりはありませんが、標題に遺言書と記載して、誰が見てもわかるようにしましょう。
封筒に入れる場合も、他の書類とまとめて捨てられないように遺言書と記載した方がいいかと思います。
自筆証書遺言に関しては、法務局で保管するもの制度を活用した場合を除いて、後から検認の手続きが必要となりますので、別途、遺言書以外にメモなので家庭裁判所の検認手続きが必要と記載したり、誰々に相談してくださいと記載するのも良いかと思います。
家庭裁判所の検認の手続きですが、検認を受けないと過料に処せられる可能性もあります。
判例で全体的に1通の遺言書であることが外形的に確認できれば良いとされていますが、後から争いの種にならぬように、遺言書が複数枚になった場合は、遺言書に押した印鑑で契印をしてください。
遺言を訂正する場合は、普通の訂正方法ではいけませんので、自分で遺言書を書く時は書き直した方がいいかと思います。
まとめ
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など種類があります。
自筆証書遺言は自分で保管するしか方法はありませんでしたが、法務局で自筆証書を保管できる制度ができ以前よりも選択肢が増えました。
遺言書を書く際に、用紙や筆記用具などに細かい法律の規定はありませんが、実務上気を付けなければならないことも沢山あります。
ご自身で遺言書を書く場合は、事前に知識を入れてから、遺言を作成するようにしてください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。