遺言書を作成する際には、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選ぶことができます。自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で遺言内容を全て書き記す遺言書のことです。しかし、公正証書遺言とは異なり、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを経る必要があります。本記事では、自筆証書遺言の検認手続きについて詳細に解説します。
広告
自筆証書遺言の基本知識
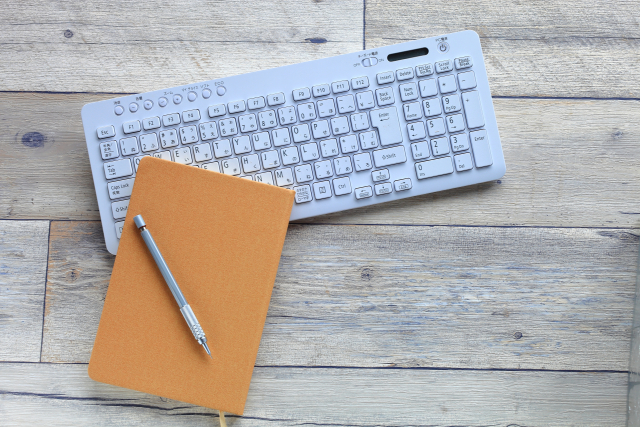
自筆証書遺言遺言の基本知識については以下の通りです。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で遺言書を書き、それを署名して作成する遺言書です。遺言者の意思を直接反映させることができ、証人が不要で手軽に作成できる点が特徴です。しかし、その一方で、法律的に有効な形式を満たしていない場合や、偽造・変造のリスクが伴います。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言の主なメリットは次の通りです。
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 他人の介入を受けずに作成できる
一方、デメリットは次の通りです。
- 法的要件を満たさない可能性がある
- 偽造・変造のリスクがある
- 紛失や破損のリスクがある
自筆証書遺言の検認手続きとは?

自筆証書遺言の検認手続きについては以下の通りです。
検認手続きの目的と重要性
検認とは、遺言書の有効無効を判断するものではなく、遺言書の形式的な状態を調査・確認する手続きです。検認の主な目的は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存することです。
検認手続きが必要な場合
家庭裁判所での検認手続きは、法務局で自筆証書遺言を保管している場合、公正証書遺言を除いて全ての遺言書に必要です。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言などは検認手続きを経ないと、金融機関での手続きや法務局での相続登記ができません。
広告
家庭裁判所での検認手続きの流れ
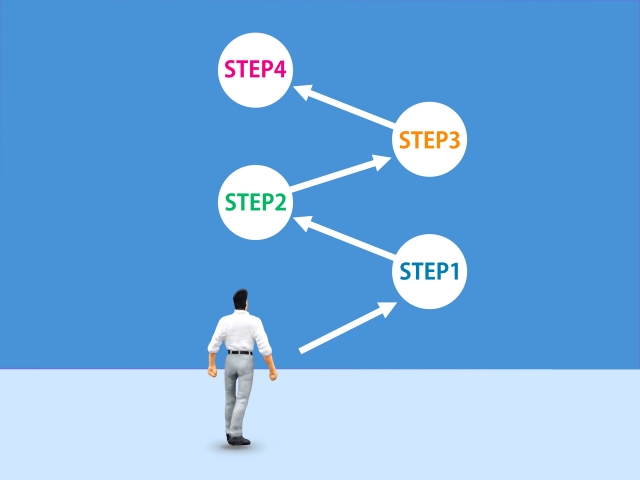
家庭裁判所での検認手続きの流れについては以下の通りです。
検認手続きの準備
検認手続きを始める前に、まず遺言書の保管者や相続人は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立てには、遺言書の原本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが必要です。
検認の申立て方法
申立ては、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に出向いて行います。申立書には、遺言者の氏名、住所、死亡日、遺言書の種類などを記入します。
裁判所からの通知と対応
申立てが受理されると、家庭裁判所は申立人及び相続人に対して検認期日の通知を行います。検認期日には、相続人が立ち会う必要があります。
検認手続き当日の流れ
検認手続き当日は、家庭裁判所に遺言書を持参し、相続人全員が立ち会いのもとで手続きが進められます。裁判所の担当者が遺言書を開封し、その形式的な状態を確認します。この確認作業には、遺言書の内容が法律的に適正かどうかの判断は含まれていません。形式的な確認とは、遺言書の署名や日付が適正に記載されているか、内容が書き加えられたり削除されたりしていないかなどを確認するものです。
検認済証明書の発行
検認手続きが終了すると、家庭裁判所は申立人に対して検認済証明書を付した遺言書を返還します。この証明書は、遺言書が正式に検認されたことを証明するものであり、金融機関や法務局などでの手続きに必要となります。
広告
検認手続きに必要な書類と費用

検認手続きに必要な書類と費用は以下の通りです。
必要書類のリスト
検認手続きには主に以下の書類が必要です。
- 遺言書の原本
- 遺言者の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 検認申立書
検認手続きにかかる費用の詳細
検認手続きには手数料がかかります。通常、検認申立ての手数料は数千円程度ですが、具体的な費用は家庭裁判所によって異なる場合があります。また、手数料の他に、戸籍謄本や住民票などの取得費用もかかるため、総額で1万円前後の費用を見込んでおくと良いでしょう。
検認手続きのポイントと注意点

検認手続きのポイントと注意点は以下の通りです。
手続き中に起こり得るトラブル
検認手続き中に起こり得るトラブルとしては、相続人間の紛争や、遺言書の内容に関する異議申し立てがあります。これらのトラブルを未然に防ぐためには、遺言書の内容を明確に記載し、信頼できる証人を立てることが重要です。また、遺言書の保管場所についても、信頼できる人に預けるか、法務局に遺言書を保管するか安全な場所に保管するようにしましょう。
検認後の遺言執行の流れ
検認手続きが終了すると、申立人に対して検認済証明書を付した遺言書が返還されます。その後、遺言の内容に基づいて遺言執行者が相続手続きを行います。遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実行し、相続財産の分配や名義変更などを行います。
広告
行政書士のサポートを受けるメリット

行政書士のサポートを受けるメリットは以下の通りです。
専門家のサポートで手続きがスムーズに
行政書士に依頼することで、相続手続きがスムーズに進みます。行政書士は、遺言書の作成から相続手続きまでトータルサポートを提供します。(家庭裁判所の検認手続きは代行できません)特に、自筆証書遺言の検認手続きに関しては、書類の準備や申立ての方法、手続きの流れについて専門的なアドバイスを受けることができます。
トラブル防止とリスク管理
行政書士を利用することで、遺言書の法的要件を満たし、トラブルやリスクを未然に防ぐことができます。また、遺言執行時の手続きも円滑に進めることができます。遺言書の内容が明確であること、法的に有効であることを確認するために、行政書士のサポートは非常に有効です。
広告
まとめ
自筆証書遺言の作成や検認手続きには、法的な知識と経験が必要です。行政書士のサポートを受けることで、遺言書の作成から検認手続き、相続手続きまでをスムーズに進めることができます。遺言書を作成する際には、適切な形式を守り、検認手続きを経て正式な遺言書としての効力を持たせることが重要です。相続人が煩雑な手続きを避けるためにも、行政書士に依頼し、安心して遺言の執行を進めることを検討しましょう。当事務所でも遺言書の作成のサポートを行っております。ご依頼をご検討の方は問い合わせフォームからご相談いただければ幸いです。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。





