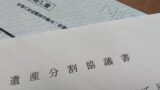死後離婚とは、正式な言葉ではありませんが、配偶者が亡くなった後に、生存している配偶者が市町村長に対して「姻族関係終了届」を提出することを指します。
配偶者が亡くなった後に、配偶者の親族との関係を続けることに抵抗を感じる方もいらっしゃるでしょう。特に、配偶者が生前に親族との関係が良好でなかった場合、その後も関係を続けることは難しいかもしれません。
今回の記事では、配偶者が亡くなった後に姻族関係を終了させる手続きや氏を変更する手続きについて解説します。
姻族関係終了届とは

配偶者が亡くなった後に、配偶者側の親族と関係が良好でなかったりして、配偶者が亡くなった後も配偶者の親族と関係を続けたくないと考えられる方もいらっしゃると思います。
そういった場合には、本籍地または住所地の市区町村の役所に、姻族関係終了届を提出することによって、姻族関係を終了させることができます。
そもそも姻族とは、婚姻によって生じた親族関係のことをいいます。
親族の範囲は民法725条で6親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族が親族とされています。
義理の兄弟や義理の両親をイメージした方がわかりやすいかもしれません。
(親族の範囲)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
姻族とは何か

姻族とは、婚姻関係による配偶者の血族または自分の血族の配偶者をいいます。
具体的には、自分の配偶者の父母や、自分の兄弟の配偶者などが姻族となります。
姻族は婚姻関係により生じる間柄ですので、婚姻関係の解消に伴い姻族としての関係も終了しますが、配偶者が死亡した場合は姻族関係が当然に終了するわけではありませんので注意が必要です。この場合は姻族関係終了届という届出により手続きを行うことで姻族関係を終了させることが可能になります。
配偶者が亡くなった後に配偶者側の親族と関係が良好でなかったりして、配偶者が亡くなった後も関係を続けたくないと考えられる方もいらっしゃると思います。
そういった場合には、姻族関係終了届を提出することによって、姻族関係を終了させることができます。
配偶者が亡くなったとしても姻族関係は終了しない
配偶者が亡くなっても、姻族関係が終了するわけではありませんので、親族としての関係は維持されてしまいますので、特別の事情がある時には家庭裁判所の審判によって、三親等内の親族に対して扶養義務が発生してしまう可能性があります。
広告
扶養義務とは

扶養義務とは、自分の収入だけでは生活を成立させることができない親族がいる場合に、仕送りや現物支給などにより、経済的な援助を行う義務を意味します。扶養義務者は、被扶養者から扶養を請求された場合には、協議または家庭裁判所の判断により、一定の経済的援助を行わなければなりません。
扶養義務者には、原則として直系血族と兄弟姉妹が含まれます。このうち直系血族には、父母・祖父母・曾祖父母(そうそふぼ)・子ども・孫・ひ孫などが該当します。また、夫婦間には、民法第752条に基づく相互協力扶助義務が定められています。その一環として扶養義務があると解されているので、被扶養者の配偶者にも、扶養義務が認められます。
扶養義務は、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の二つに分けられます。「生活保持義務」とは、被扶養者の生活を扶養義務者の生活水準と同程度に維持しなければならない義務をいいます。生活保持義務を負うのは、被扶養者の配偶者と、未成年の子どもである被扶養者の両親です。これに対して「生活扶助義務」とは、自分の親、祖父母などの直系尊属及び兄弟姉妹に対する扶養義務で、扶養義務を負う者の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで余力のある範囲で援助する義務です。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
姻族の扶養義務とは
基本的に、姻族は直系血族ではないため、原則として扶養義務を負いません。しかし、特別な事情がある場合には、家庭裁判所は、3親等内の親族間でも扶養義務を生じさせることができます。
因みに特別な事情とは、例えば直系血族や兄弟姉妹が経済的に扶養が困難な場合などを指すと考えられます。しかし、具体的な事例や判断基準は、個々の事情や家庭裁判所の判断によります。
特別の事情がある場合には、家庭裁判所の審判により、被扶養者と3親等内の親族に対しても、扶養の義務が課されることがあります。家庭裁判所の審判により特別に扶養義務を課される可能性があるのは、伯父(叔父)、伯母(伯母)、おい、めいなどです。
離婚は姻族が終了するのに配偶者が亡くなっても姻族が終了しない理由
離婚の場合は姻族関係理由は、離婚はお互いの意思が反映されていますので当然に姻族関係の解消も望んでいると考えられます。しかし、配偶者の死亡の場合では当然に婚姻関係の解消を望んでいるわけではありません。原則として当事者の意思の違いがこのような違いとなるのです。
姻族関係終了届の提出先などは
配偶者と離婚した場合は、配偶者の親族も含めて姻族関係は終了しますが、配偶者が亡くなった場合は当然に姻族関係が終了するわけではありませんので、姻族関係終了届出を提出します。
具体的な方法として、姻族関係終了届は、配偶者本人の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。この届出は戸籍の記載や氏、配偶者としての相続権に影響を与えません。
氏を変更したい場合は、別の届出が必要となります。また、姻族関係終了届の提出には、姻族の同意は必要ありません。生きている配偶者の意志だけで提出が可能です。
広告
配偶者が亡くなった後に名字を戻したい場合

復氏届を提出することによって名字を元に戻すことができます。
復氏届は、結婚して配偶者の名字を名乗っていた人が、配偶者の死亡後、旧姓に戻す手続きです。この手続きは、本籍地または住所地の役所に提出するだけで、裁判所の許可や配偶者の親族の同意は必要なく、本人の意思のみで自由に提出できます。また、提出に期限はありません。
復氏届を提出すると、配偶者の戸籍から抜けることになります。しかし、配偶者の相続人という地位は奪われず、配偶者の遺産を相続する権利は残っています。また、姓を変更するからと言って配偶者と離婚したわけではありませんので、配偶者の親族(義父母や配偶者の兄弟姉妹)との法律上の関係は変わらず、扶養義務も残ります。
姻族関係を終了するには、先ほど解説した姻族関係終了届が必要です。
未成年の子供と一緒に元の名字になりたい場合
復氏届を提出すると配偶者の戸籍から抜けることになりますので、結婚前の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作るかを選ばなくてはなりません。
子どもがいる場合、復氏届は届出をした本人のみの変更であり、子どもへの影響はありませんが、子どもが未成年であった場合、復氏届を提出するなら子供と一緒に自分の戸籍に移したいと考える方もいます。
自分と同じ名字を名乗らせたい、自分の戸籍に移したいというのであれば、子どもの名字を変更する許可を取るため、裁判所に申し立てなければなりません。そして、死亡した配偶者の戸籍から離脱させ、自分の戸籍に移すという手続きをすることになります。
広告
まとめ
配偶者が亡くなった後に、配偶者側の親族と上手くいってなくて、名字を元に戻したり、姻族としての関係を終了させたいと考えることもあるでしょう。
親族であると扶養義務が生じる可能性もありますので、姻族関係終了届出を提出する意味はあるかと思います。
手続きをする際には、提出先によって書類が若干異なる可能性もあるため、事前に市区町村役場の担当窓口に問い合わせをしましょう。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。