設立趣旨書は、NPO法人設立の最初にして最も重要な書類の一つです。単に理念を述べるための文章ではなく、審査を行う所轄庁に対して「この法人がなぜ必要で、どのように実現するのか」を明確に説明するための実務文書です。この記事では、設立趣旨書が持つ役割と、なぜ作成に行政書士の関与が有効なのかを整理します。
設立趣旨書の役割と審査官が見ているポイント

この節では、審査官が実際にどの点を重視するのか、設立趣旨書で押さえるべき観点を分かりやすく解説します。
審査官が重視する観点
- 法適合性
NPO活動が法律で想定された分野に含まれるかを見ます。ここでのポイントは、単に社会貢献的であるだけでなく、法の下で規定された「特定非営利活動」に該当することを明確に説明することです。分野名(例:福祉、まちづくり)と具体的な活動の関係性を文章で示しましょう。 - 社会的必要性
問題の存在を客観的に示すために、統計データや行政報告、地域の実情などを用いて裏付けをします。単なる感覚的表現は説得力に欠けるため、数値や公的資料の引用を適切に入れることが重要です。 - 事業の具体性
単に「支援を行う」と書くのではなく、対象(誰が)、方法(何を)、頻度(いつ)、場所(どこで)、協力先(誰と)、参加者数の想定まで示すことが望まれます。具体性が高いほど審査官は実施可能性を評価しやすくなります。 - 実現可能性
体制(理事・スタッフの役割)、資金(概算予算・収入見込み)、協力体制(連携先の存在や合意)が示されているかを確認します。特に当面の資金繰りや人的確保の見通しは重要です。 - 評価方法
事業の成果をどのように測るか(KPI)と、その評価結果をどのように事業改善に結びつけるかの検討が求められます。定性的な評価だけでなく、定量的指標を入れることが望ましいです。
所轄庁と提出手続きの流れ

ここでは、どこに何を出すべきか、申請から認証・登記までの流れを実務の視点で解説します。期限や公開される情報、所轄庁ごとの取り扱い差など、現場でトラブルになりやすいポイントを丁寧に説明します。
提出先の基本ルールと注意点
提出先は基本的に主たる事務所所在地の所轄庁です。都道府県庁や政令指定都市の区別、事務所の所在地が複数ある場合の扱いなど、判断を誤ると書類が受理されないため注意が必要です。また、所轄庁によって様式や添付書類の扱い・公開方法が異なるため、事前に所轄庁の最新案内を確認し、可能なら手引書をもらうと安全です。
申請から認証までの流れ
- 申請書提出
定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書などを揃えます。役員については住所を記載した名簿の提出が必要ですが、令和2〜3年の法改正により、所轄庁が縦覧・公表する際には住所部分は非公開となっています。提出と公表の扱いを混同しないよう注意してください。書類の体裁(順序・ファイル名・押印)は所轄庁の要領に従って整えます。 - 公衆縦覧(受理日から2週間)
法令で定められた期間です。一部の書類が一般に公開され、意見を受付けます。記載内容を事前に確認し、第三者に誤解される表現がないか注意してください。 - 審査・補正対応(縦覧終了後2か月以内に決定)
所轄庁は縦覧終了後、原則として2か月以内に認証または不認証の決定を行います。補正を求められた場合は期限内に対応が必要です。条例で期間を短縮している所轄庁もあるため、スケジュールは必ず最新の要領を確認してください。 - 認証後の登記(通知を受けてから2週間)
登記完了により法人が成立します。登記申請を怠ると認証取消の要因になるため、認証通知を受け取ったら速やかに登記手続きを行う体制を整えます。 - 登記完了後の届出
登記事項証明書や財産目録を所轄庁へ提出します。提出様式や添付書類は所轄庁ごとに異なるため、登記前に確認しておくと二度手間になりません。
広告
設立趣旨書の推奨構成

設立趣旨書は、審査官が読みやすく、かつ必要な情報が短時間で把握できることが求められます。本節では、読みやすさと正確性を両立するための構成と、各ブロックで盛り込むべき具体的要素を詳しく説明します。
推奨される8つの構成要素
- タイトル行
団体名と目的を一行で示します。長いキャッチフレーズは避け、審査官が瞬時に要旨を掴める表現を心がけてください。 - 冒頭サマリ(推奨200〜400字程度)
文章の冒頭で要点をまとめます。課題、目的、主要事業を簡潔に示すことで、審査官に全体像を早く理解してもらえます。※法令上の要件ではなく、読みやすさのための目安です。 - 社会的背景(客観データ)
地域の人口動態、関連する行政データ、既存の支援体制のギャップなどを示します。出典を明示することで信頼性が高まります。 - 目的(1文)
誰に、どんな価値を提供するのか、変化の見込みを1文で表現します。簡潔かつ測定可能な表現が望ましいです。 - 主要事業(箇条書き)
個々の事業について、対象・手法・頻度・場所・協力先・想定参加者数を記載します。事業ごとに期待される成果を短く付記すると効果的です。 - 実施体制と資源
理事・スタッフの役割分担、外部協力の有無、ボランティア数の見通し、初年度の予算配分など、実現可能性を裏付ける情報を示します。 - 期待される効果と評価方法
定量目標(例:初年度の参加者数)や観察指標(例:相談件数、満足度)を設定し、定期的な評価スケジュールを示してください。 - リスク管理・個人情報保護
安全管理規程の有無、個人情報の取り扱い方針、活動中の事故対応フローなどコンプライアンス面を簡潔に示します。
書き方のポイント

設立趣旨書の書き方は技術です。説得力のある設立趣旨書は、論理的な構成と客観的根拠、実行計画の3点が整って初めて成立します。ここでは具体的な表現テクニックを詳述します。
表現テクニックと注意点
- 根拠→目的→方法の流れを厳守する。読者(審査官)に「なぜ」「何を」「どうやって」を一貫して示すことが重要です。
- 定量目標は可能な限り明示する(数値がないと達成判定が困難)。年度ごとのKPIを最低1〜3項目用意しましょう。
- 事業フローを図や段階で示す:準備期、実施期、フォローアップ、評価というフェーズ分けを示すと実施計画の輪郭がつかめます。
- 所轄庁の記載例に合わせる:表題名や項目名が求められている場合は、その様式に忠実に従うことで形式面の差戻しを避けられます。
- 過度な宣伝文句は避ける:公共性と具体性が求められるため、感情的な言葉づかいは抑え、事実と計画に基づいた表現を優先してください。
広告
具体サンプルと解説
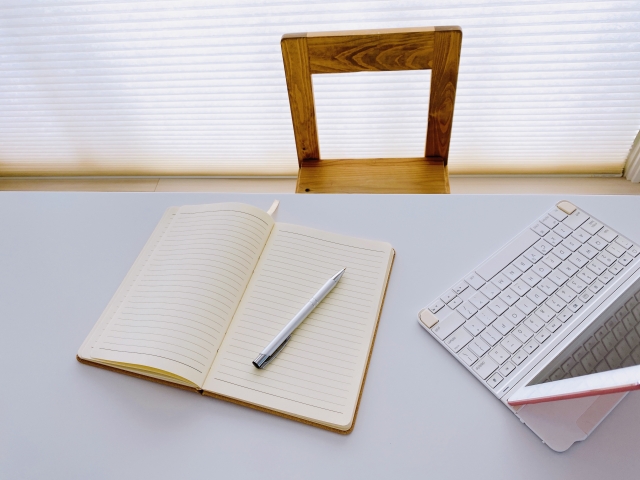
実際にどのような文章が審査で受け入れられやすいのか、サンプルを示したうえで、なぜその構成が有効なのかを解説します。サンプルは短めにまとめ、審査官が求める要素を網羅しています。
本法人は、○○市における高齢者の孤立防止を目的とし、交流・相談の場を恒常的に提供する。主要事業は(1)月1回の交流会、(2)月2回の見守り訪問、(3)相談窓口の運営である。地域包括支援センターや医療機関と連携し、初年度は延べ参加者300名、相談対応200件を目標とする。運営は理事○名、会員○名の体制で行い、個人情報は安全管理規程に基づいて取り扱う。
このサンプルが有効な理由
サンプルは目的・事業・目標・体制・個人情報保護の順で情報を提示しており、短文で審査官が期待する情報を提供しています。特に数値目標と連携先の明記が実現可能性を支える要素です。
よくある不備と回避策
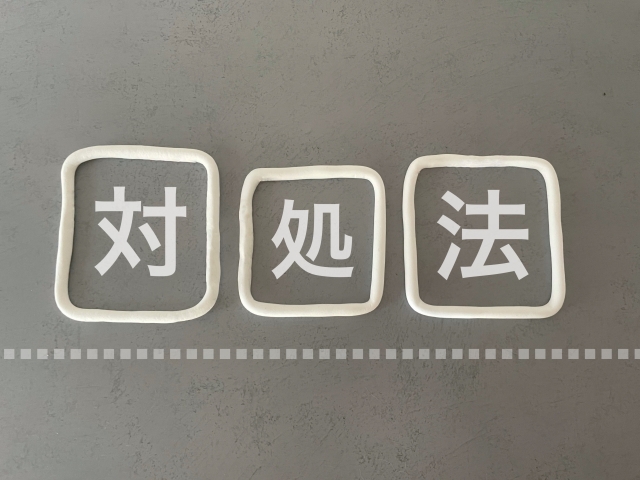
審査で指摘されやすいポイントを把握し、あらかじめ対策を講じれば補正回数を減らせます。本節では典型的な不備と具体的な改善策を、実務目線で示します。
主な不備と改善ポイント
- 目的と事業がかみ合わない:事業ごとに「解決する課題」を明記し、目的との因果関係を文章で示す。
- 体制の裏付けが弱い:主要メンバーの経歴や過去の実績、外部協力団体の合意書や面談メモを添付すると説得力が増します。
- 財務計画が曖昧:項目別の初期費用、運営費、収入見込み(会費、補助金、寄付等)を簡潔に示す。リスク時の資金繰り方(予備資金等)も説明すると安心感を与えます。
- 所轄庁様式に不一致:提出前に最新の様式と突合し、ページ番号・項目名が合うか確認してください。
広告
提出前チェックリスト

最終確認は重要です。審査で指摘されやすい箇所を漏れなくチェックするために、本チェックリストを活用してください。特に初めての申請ではチェック漏れが多いため、第三者によるダブルチェックを推奨します。
提出前の必須チェック項目
- 冒頭サマリが200〜400字で要旨を伝えているか(長すぎないこと)。
- 社会的背景に出典があるか(データの出所を明記)。
- 各事業に対象・頻度・実施主体・協力先・想定人数が書かれているか。
- 実施体制(理事・スタッフ)と予算根拠が示されているか。
- 成果指標(KPI)と評価方法が明確か。
- 最新の所轄庁様式と照合済みか。
これらは一般的な要件です。所轄庁によって異なる可能性があります。
認証後の実務フロー
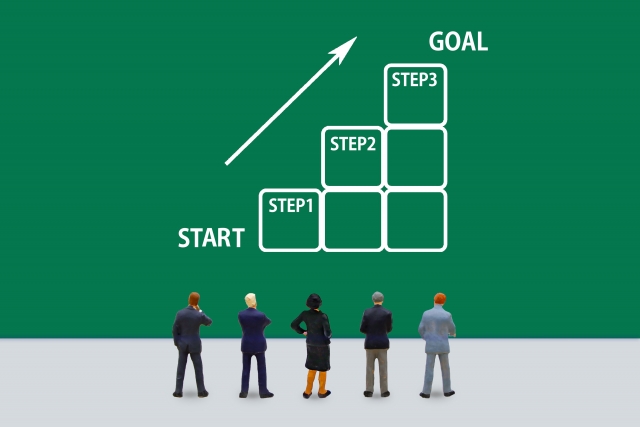
認証を得た後も手続きは続きます。認証から登記完了、届出までの期限が短い点は実務でよくトラブルになるため、ここでは各フェーズの留意点と実務的な進め方を詳述します。
認証までの注意点と実務アドバイス
- 受理日から2週間:縦覧 ・縦覧期間の公表内容に個人情報が含まれていないかを事前に確認しましょう。
- 縦覧終了後:原則2か月以内に認証可否決定
・所轄庁から補正依頼が来る可能性を想定してスケジュールに余裕を持たせてください。 - 認証通知を受けてから2週間以内に登記申請
・登記申請は司法書士と連携する場合が多いため、事前に連絡先と役割分担を明確にしておくとスムーズです。 - 登記完了後:登記事項証明書+財産目録を届出
・届出様式は所轄庁ごとに異なるため、登記が完了する前に確認しておき、必要な書類を揃えておきましょう。
また、認証後6か月以内に登記をしなかった場合は認証取消のリスクがあるため、必ずスケジュール管理を行ってください。
広告
行政書士が提供できる付加価値

行政書士は申請書類の作成にとどまらず、事前準備から認証後の届出まで一貫してサポートできます。本節では、具体的なサービス項目とそれが顧客にもたらす効果を説明します。
提供可能なサービスと利点
- 所轄庁の様式に合わせた文書体裁の整備:形式面のミスを防ぎ、受理率を高めます。
- 事業計画と予算書の整合性チェック:実現可能性を高め、補正リスクを減らします。
これらをワンパッケージで提供することで、顧客の不安を軽減し、申請手続きを効率化できます。
広告
まとめ
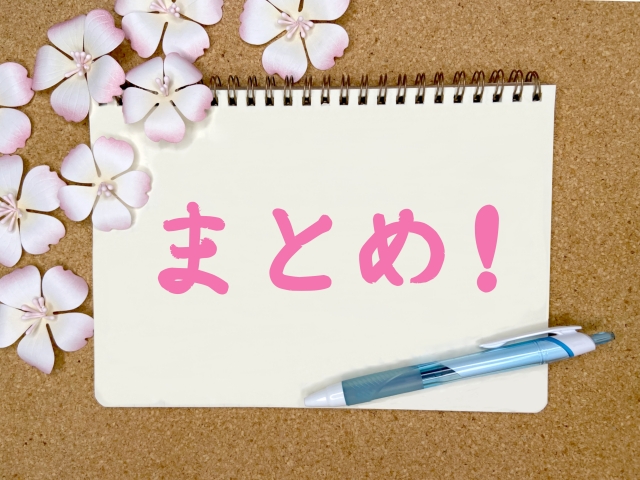
- 設立趣旨書は「審査に答える実務文書」であり、根拠・具体性・実現可能性が肝心です。
- 所轄庁の様式に合わせ、数値や出典を盛り込み、体制と資金の裏付けを示しましょう。
- 認証後の期限(登記等)は短いため、事前にスケジュールを整え、専門家と連携することが成功の鍵です。
設立趣旨書は「理念を語る文章」ではなく「審査に答える実務的な書類」であり、団体の将来を左右する重要なポイントです。しっかりと根拠を示し、具体的で実現可能な内容に仕上げることが、認証をスムーズに進める最大の近道になります。
当事務所では、NPO法人設立に必要な書類作成やチェック、所轄庁ごとの様式調整、さらには事業計画や予算書との整合性確認までトータルでサポートいたします。これからNPO法人設立を検討される方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。





