NPO法人を設立した後に、従業員を事業が順調に行き、従業員を雇用したいと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、NPO法人でも株式会社と同様に雇用保険などの手続きが必要なのでしょうか。
今回の記事では、NPO法人が従業員を雇用するにはどうすれば良いのか一般的な解説をしていきたいと思います。
当事務所では、労働保険などの個別具体的な案件に関しては、提携の社労士事務所をご紹介しております。
NPO法人で従業員を雇用するには

NPO法人で従業員を雇用したい場合は、株式会社などの法人と同様に、労働基準法を遵守する必要があります。
労働基準法が適用される労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払う者とされているため、労働を提供してそれに対して賃金を支払っていれば、労働者となります。
NPO法人でも株式会社でも、労働の対価として賃金を支払っていれば、労働基準法を守る必要があります。
ただ、NPO法人には、ボランティアが存在するところが多いです。
ボランティアが労働者に該当するかというと、NPO法人と、ボランティアには、使用従属関係にないため、労働者には該当しません。
一定の謝礼をもらっている有償ボランティアの場合は、勤務の実態から判断されるため、後からトラブルにならないように、社会保険労務士などに相談が必要です。
広告
NPO法人はどこで従業員を雇用しているのか
事業を拡大すると、人手が必要となり従業員を雇用したいと考えることもあると思いますが、NPO法人の活動には強い想いがあると思いますので、できれば自社の活動内容などに共感してもらいえる従業員を雇用したいと考えることも多いです。
求人募集の方法として、ホームページやSNSを活用して応募がくれば良いのですが、人手不足など地域によって差もあるため、一般的な方法として、ハローワークへの求人申し込みをする方法があります。
ハローワークで事業所登録シート求人申込書を記入することによって、求人票という形で求職者が閲覧することができますので、幅広い人材を募集することができるようになるかと思います。
労働契約労働条件通知書の作成

NPO法人でも従業員を雇用するときには、労働契約を締結して、就業規則の説明を行う必要があります。
労働基準法で従業員を雇い入れる時には、労働条件通知書にて、法律で必ず記載しなくてはならない事項である絶対的明示事項と、法律で記載が義務付けられてはいませんが、会社に該当する制度がある場合は明示する必要がある相対的明示事項があります。
労働条件通知書は従業員とのトラブルを防止するためにも大切ですので、同じ内容の物を2通作成して、雇用主が記名押印して雇用主と労働者で1通ずつ保管したほうがよいでしょう。
因みに、ボランティアは労働者ではないため、労災保険や雇用保険の適用もなく、労働条件通知書も作成する必要はありませんので注意してください。
労働条件の明示)
労働基準法 | e-Gov法令検索より引用
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
就業規則の作成
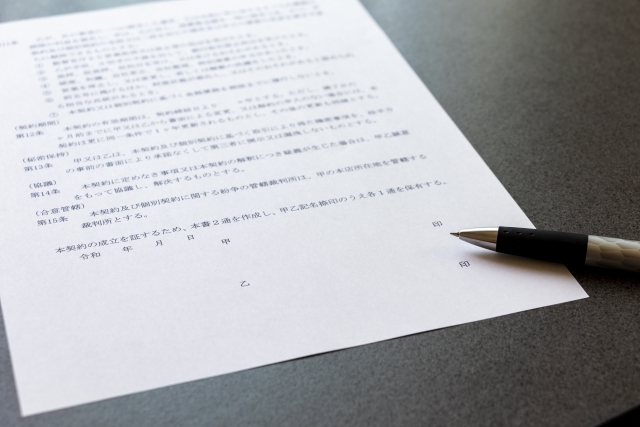
他にも、常時10人以上(アルバイト・パートも含む)の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成して、労働基準監督署への届出が必要となります。
これば、株式会社だけではなく、NPO法人でも常時10人以上の従業員を使用する場合には届出が必要となります。
ただし、ボランティアは対象とならないため、労働者としての数にカウントされません。
| 必ず記載すべき事項(絶対的明示事項) | 定めた場合には必ず記載すべき事項(相対的明示事項) | 記載するかどうか自由な事項 |
| 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金に関する事項、昇給、退職に関する規定 | 退職手当、賞与、食費 災害補償、表彰・制裁その他に関する規定 | 服務規律・誠実勤務・守秘義務等に関する事項、指揮命令や人事異動に関する事項、施設管理、企業秩序維持に関する事項、能率の維持向上その他の協力関係に関する事項、職務開発等知的所有権に関する事項など |
(作成及び届出の義務)
労働基準法 | e-Gov法令検索より引用
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労働保険とは

NPO法人でも従業員がいる場合には、労働保険に加入しなくてはなりません。
労働保険には、労働者災害補償保険と雇用保険があります。
労働者災害補償保険とは、有給職員が業務上の原因により、負傷したり病気になったり死亡した場合にその職員や遺族を保護するため必要な給付を行うものです。
雇用保険とは、従業員が失業をしたり、倒産などで雇用の継続が困難になった場合に生活、雇用の安定と再就職を促進するために必要な給付を行います。
広告
労働保険の加入
労働保険は、法人や任意団体を問わず、従業員を1人でも雇用したときは労働者災害補償保険法により強制適用事業となりますので、原則として加入しなくてはなりません。(原則、理事、監事は対象となりません)
NPO法人は一元適用事業所として、労災保険と雇用保険を併せて保険料の算定、申告、納付を一元的に処理します。
二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告、納付等をそれぞれ別個に行う事業の事をいいます。(農林漁業、建設業など)
労働保険の手続きをする管轄について

労働保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所が管轄となりますので、そちらで手続きを行う必要があります。
基本的に、先に労働基準監督署に届出をしてから、公共職業安定所の手続きをする必要があります。
流れとして、労働基準監督署で各事業所の労働保険番号が付与されますので、その番号を使って公共職業安定所へ届出を行うことになります。
広告
労働基準監督署
| 提出する書類 | 提出期限 | 届出をするとき |
| 適用事業報告 | 遅滞なく | 事業を開始したとき |
| 労働保険関係成立届 | 保険関係成立日の翌日から10日以内 | 事業を開始したとき |
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日の翌日から50日以内 | 保険料を申告納付するとき |
※申請を行う際には各機関に事前に問い合わせてください
公共職業安定所に提出するもの
| 提出する書類 | 提出期限 | 届出をするとき |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置の翌日から10日以内 | 事業所を設置したとき |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得日の翌月10日迄 | 有給職員を雇用するたびに提出 |
※申請を行う際には各機関に事前に問い合わせてください
まとめ
NPO法人でも労働者を雇用する場合には、他の営利法人と同様に労働基準法が適用されることになります。
ただし、無償のボランティアは、労働基準法の適用外となります。
労働保険料の算出方法などの個別具体的な案件に関しては、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めしております。
当事務所では、様々な士業事務所と提携をしておりますので、NPO法人のお手続きのご依頼をご検討の方は、当事務所のお問い合わせフォームからご相談ください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。





