尊厳死宣言の作成は、本人の意思を明確にし、最期を「自分らしく」迎えるために非常に重要な手続きです。しかし、その手続きは少し複雑に感じることもあるかもしれません。この記事では、尊厳死宣言を作成する具体的な流れを詳しく解説します。行政書士や公証役場の利用方法も含めて説明しますので、ぜひ参考にしてください。
尊厳死宣言を作成する必要性と準備

尊厳死宣言書は、本人が延命治療を望まないという意思を明確にし、最期を自分らしく迎えるために非常に重要な手続きです。この宣言書があることで、家族や医療従事者に自分の意向をしっかり伝えることができ、不要な延命治療を避けることができます。しかし、この手続きにはいくつかの準備が必要です。まずは尊厳死宣言がなぜ必要なのかを理解し、その上で作成に向けた具体的な準備を整えていきましょう。
なぜ尊厳死宣言が必要なのか
尊厳死宣言書は、本人が延命治療を望まない意思を記録に残すものです。これを作成することで、以下のようなメリットがあります。
- 家族間のトラブルを防ぐ
親族が延命治療の選択をめぐって意見が対立するのを防ぎます。 - 医療関係者への指針となる
医師が患者の意思を尊重した対応を行いやすくなります。 - 法律的なトラブルを予防
治療中止が家族や医療関係者の責任追及につながるリスクを軽減します。
作成前の準備
尊厳死宣言を作成する前に、以下の準備を整えましょう。
- 延命治療を望まないという意思が明確かを確認。
- 家族にも意思を伝え、理解を得ておくことが重要です。
- 必要な書類の準備
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
医療に関する情報(かかりつけ医がいればその意見も参考になります)
必要な費用(公証役場での作成費用、行政書士への報酬など)
広告
尊厳死宣言作成の具体的手続き
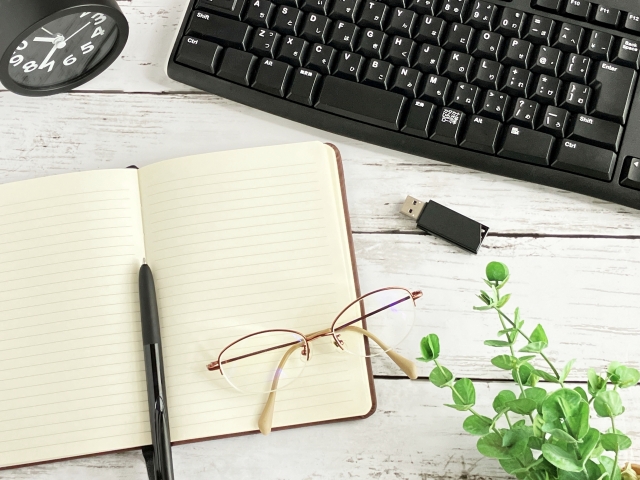
尊厳死宣言書の作成は、非常に重要な決断を記録に残す作業ですが、その手続きは思った以上に複雑ではありません。実際に宣言書を作成するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。それぞれのステップを理解し、確実に進めることで、最終的に本人の意思がしっかりと反映された尊厳死宣言書を完成させることができます。今回はその具体的な手続きの流れについて、詳細にご紹介します。
意思の明確化
最初に、自分が「延命治療を望まない」理由を明確にしておきます。たとえば、以下の内容を考えると良いでしょう。
- どのような延命治療を拒否するのか
人工呼吸器、心肺蘇生、経管栄養など。 - 苦痛を和らげる措置は望むのか
緩和ケア(ホスピスケア)を希望するか。 - 家族や医療関係者に伝えたいメッセージ
最期に対する想い。
専門家への相談
法律に詳しい専門家である行政書士に相談すると、手続きをスムーズに進められます。
行政書士の役割
- 尊厳死宣言書の文面作成をサポート。
- 家族間の意見調整の手助けを提供。
公証役場での手続き
尊厳死宣言書は、公証役場で公正証書として作成することを推奨します。以下の手順で進めます。
- 公証役場を予約
公証役場に事前予約を行い、必要書類を案内してもらいます。 - 本人確認書類を提示
運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証などが必要です。 - 公正証書の作成
公証人が本人の意思を確認し、内容を文書化します。
必要に応じて家族や第三者(立会人)の同意書を提出する場合もあります。 - 署名・押印
内容を確認後、本人が署名・押印を行います。 - 作成費用を支払う
書類の保管と共有
作成した尊厳死宣言書は、以下の場所に保管し、必要な人と共有します。
- 家族全員に内容を説明し、意識を共有します。
- かかりつけ医や病院にもコピーを渡しておきましょう。
- 紛失しないよう、信頼できる場所(貸金庫、家族との共同保管など)に保管します。
広告
尊厳死宣言を作成する際の注意点

尊厳死宣言書を作成する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを踏まえて手続きを進めることで、後々のトラブルを避け、本人の意思がしっかりと反映された宣言書を作成することができます。注意点について理解し、慎重に進めることが、尊厳死宣言書作成における成功のカギとなります。
意思能力が必要
尊厳死宣言は、本人が健康で意思能力があるときに作成する必要があります。病気が進行し、意思能力が失われた場合、書類の有効性が問われる可能性があります。
家族の理解を得る
家族が尊厳死宣言に反対すると、医療現場でトラブルが生じる場合があります。そのため、家族と十分に話し合い、理解を得ることが重要です。
定期的な見直し
状況が変化した場合に備え、定期的に内容を見直し、必要に応じて更新しましょう。
行政書士に依頼するメリット

尊厳死宣言書の作成において、専門家である行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。行政書士は、法的に正しい書類を作成するための知識を持っており、書類作成に関する不安を解消してくれます。また、家族間で意見の食い違いが生じた場合、第三者として調整役を果たしてくれるため、スムーズに手続きを進めることができます。
尊厳死宣言書の作成を専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 法的に不備のない書類の作成
専門知識を活かして、確実な書類を準備できます。 - 家族間の調整をサポート
第三者の立場で、家族間の意見調整をスムーズに行えます。 - 医療現場での信頼性が向上
行政書士や公証役場で作成された書類は、医療従事者にとって信頼性が高いです。
まとめ
尊厳死宣言書を作成することは、本人と家族の双方にとって非常に大きな安心感をもたらします。この手続きを進めるには、まず自分の意思を明確にし、信頼できる行政書士や公証役場に相談することが重要です。
「最期をどう迎えるか」というテーマは誰にとっても重要な課題です。この機会に、自分らしい最期を迎える準備を始めてみませんか?専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進み、より安心して人生を締めくくることができるでしょう。
尊厳死宣言書の作成は、大切な人生の選択を明確に示す重要な手続きです。専門家のサポートを受けることで、手続きをより確実に、スムーズに進めることができます。当事務所では、尊厳死宣言書の作成をサポートしています。経験豊富な行政書士があなたの疑問や不安にお答えし、最適な解決策をご提案します。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。






