公正証書遺言を作成する際に、公証役場に出向き公証人に遺言書を作成してもらいますが、そもそも公証役場とは何をする場所なのでしょうか。
今回の記事では、公証役場についてや、公正証書遺言の作成や証人などの制度について解説したいと思います。
公証役場とは何かどんな人が公証人になるのか

一般の方が公証役場に行くことはあまりないかと思います。
行政書士は公正証書遺言の作成や、株式会社を設立する時の定款認証の際に公証役場に行くことが多いです。
公証役場には公証人がいて業務を行っています。
公証人には、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、大半が判事や検事出身者となっています。
公証人は、いわゆる国家公務員ですが一般的な国家公務員とは違い、給料や補助金は一切支給されません。
公証人の給料にあたるものは、公証人手数料令に定められている手数料が収入源となっており、手数料収入で、公証役場を維持します。
そのため、公証人は皆さんが思っているような国から給料を貰っている公務員とは異なり、個人事業主のような形をとっています。
個人事業主のような形ですが、国家公務員でもあるため、勝手に公証役場を作り仕事をすることはできません。
公証役場は、法務省が人口動態や手数料収入の状況を勘案して公証役場の所在地を決めています。
広告
公証人の手数料は
公証役場は手数料収入で運営するため、書類を作成したり、認証する場合は手数料が発生しますが、相談料は取ってはいません。
そのため、遺言や各種契約書を公正証書で作成したいと相談するだけでは手数料は発生しません。
全国に公証役場があるがどこの公証役場に行けばいいのか
公証役場は全国にあり、どの公証役場に相談にいっても基本的には問題ありませんが、定款認証などは、管轄が決まっているため、東京の会社を設立する時に、北海道の公証役場で認証手続きをしてもらうことはできません。
公証人は管轄する範囲でしか業務を行う事ができないため、管轄外に出張してもらうこともできませんが、管轄内であれば、本人が病気で療養中の場合などの理由で本人が公証役場に出向くことができない場合には、自宅や病院などに出張してもらうことも可能です。
公正証書遺言とは

自筆証書遺言では、遺言者が自書で作成しましたが、公正証書遺言では、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べて、これを公証人が筆記して遺言者と2人以上の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、遺言者と証人が筆記が正確であることを認めて署名、押印した後、公証人が方式に従って作成したことを付記して署名、押印して作成する遺言です。(要するに遺言者が遺言書を作成するわけではなく、公証人が遺言者から聞いた内容を証人と確認して、代わりに証書として残すという意味です)
広告
(公正証書遺言)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書のメリット

公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、公証人が作成するため、遺言の方式の要件を欠いて無効になる可能性が限りなく低くだけでなく、遺言を書くための意思能力・遺言の内容が詐欺、強迫によってなされていないことを証明するという意味もあり、後から遺言の効力を巡って争いになる可能性も低いです。
他にも体の不自由な方で、まったく字が書けない方や、口がきけない方でも公正証書を作成することができます。
最近では、遺言書を法務局で保管する制度ができましたが、公正証書遺言でも遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や、相続人による破棄、隠匿などの可能性がありませんし、家庭裁判所で検認をする必要もないため、遺言者が亡くなった後に相続人は、不動産登記や金融機関などの手続きがすぐにできます。
公証証書のデメリット
公正証書の作成には、デメリットもあります。
まず、事前に公証人とやり取りする必要があり、登記簿謄本や不動産がある場合には、固定資産評価証明書などの書類が必要ですし、公証人に手数料を支払わなくてはなりません。
他にも、公証人だけではなく、証人も遺言の内容を聞いているため、外部に漏れる可能性があります。
ただ、公証役場で証人を依頼した場合は、守秘義務のある行政書士や司法書士などが選ばれることが多いため、リスクは低いと考えられます。
広告
公正証書遺言で必要な証人とは
公正証書遺言を作成する際の証人について、遺言者側で用意する場合は要件などはあるのでしょうか。
結論から言うと、誰でも良いわけでなく親族など遺言書を作成する際に関係があるであろう人物は証人になることができません。
民法974条で、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人は証人になることはできません。
要するに、遺言者の子供(推定相続人)や遺言で遺贈を受ける予定の人物は証人になれず、遺産をもらう本人以外の配偶者、未成年者も証人になることができません。
これは、証人が遺言について利害関係があると、公正な立場で遺言について証言できないと考えているからです。
ただし、推定相続人の規定は、第一順位の推定相続人というのが通説となっているため、遺言者に子供がいれば、第二順位の親だとか兄弟は証人になることができます。
公正証書遺言を作成する際には、上記の規定があるため、基本的には遺言者と全く親族関係のない友達など他人か、行政書士などの士業に公正証書遺言の証人を頼むが良いかと思います。
証人は公証役場でその氏名、生年月日、住所、職業を公証人に告げて、住民票や免許証の写しなどを提出して、日程を合わせて公証役場に行くことになります。
あまり忙しい方だと、平日に予定を合わせるのは厳しいかもしれません。
(証人及び立会人の欠格事由)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人が用意できない
あまり近所付き合いをしていない場合や、友人がいても都合がつきそうな人がいない場合は公証役場に証人の手配を依頼することも可能です。
そういった場合には、公証役場に出入りをしている行政書士、司法書士などの士業に公証役場から連絡が入り証人になることが多いです。
証人を頼む際には謝礼を払うのが一般的ですので公証役場で金額を確認してください。
広告
公正証書遺言の原本とは
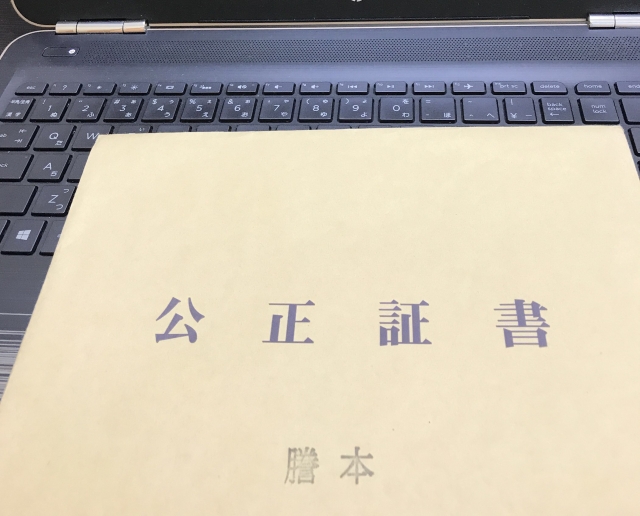
公正証書のい原本とは、一定の内容を表示するため確定的なものとして作成された文章で、正本や謄本のもとになる文章をいいます。
原本には嘱託人等の署名押印があり、印鑑登録証明書、免許証の写しなどの付属書類が一緒に保管されています。
原本に関しては、公証役場に保存されているため、書類を外部に持ち出すことができません。
公正証書遺言の正本とは
原本の正規の複製証書の事を正本といいます
正本には 正本である旨の公証人の認証があり、原本と同じ効力を有する文章です
原本は公証役場に保存されていて 持ち出しができないために 相続の手続きをするときに、遺言を持参する際に必要です。
公正証書遺言の謄本とは
正本と謄本は原本の正規の複製証書という点で変わりがありませんが
原本と同じ効力はなく内容を確認するための複製証書です。
公正証書遺言の保存期間
公正証書遺言は公証役場に厳重に保存され、通常20年間は保存されます。
保存期間が経過した場合は破棄されますが、公正証書遺言の場合は、長寿化の影響もあり、原則として遺言者が120歳になるまで保存されることが多いです。
広告
公正証書遺言を作成しているときに誤記があった場合はどうするか

公正証書遺言の作成の過程で、誤記があった場合は、文字を訂正することになりますが、その方法は公証人法の38条に規定があり、文字の挿入をするときは、その字数及びその箇所を欄外または末尾の余白に記載して、公証人と嘱託人またはその代理人が押印します。
文字を削除する時も、文字が読み取れる状態にして、削除した字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載して、公証人及び嘱託人またはその代理人が押印する必要があります。
公正証書遺言の場合の誤記は上記のように行いますが、押印をするのは、公証人、嘱託人、遺言者と証人となります。
作成後に誤りに気付いた場合
公正証書を作成した後に誤記が分かった場合にはどうすればよいのでしょうか。
公正証書を作成した後に誤記を発見した場合は、公証人が誤記証明書を作成することになります。
誤記証明書には公証人が、誤記部分を特定して、その正しい記載内容とその根拠資料を記載して、署名押印して作成をします。
ただし、誤記証明書で更正できる事項は明白な誤記、遺脱に限られますので、当該証書の付属書類や戸籍謄本・登記簿謄本等の関係書類または当該証書の他の記載部分に照らして明白な場合に限られるため、何でも訂正できるわけではありません。
誤記証明書がないと不動産の表示を間違えて記載した時に、不動産登記などの手続きができなくなってしまうため、公証人の誤記証明書によって手続きを進めることをできるように実務上取り扱いをされています。
広告
まとめ
公証役場は当事者の将来の紛争を予防することが主な役割です。
公証人の作成する書類は、法人設立の際の定款認証や各種私文書の認証など、多岐にわたります。
公正証書は、公証人(裁判官、検察官、弁護士、法務局長経験者等)が作成するため、基本的に要件の不備などは心配する必要なく、遺言者の意思能力や遺言の偽造、変造、隠匿、紛失の恐れも限りなく低いです。
遺言者の死後に家庭裁判所に検認の申し立て手続きをする必要もありませんので、基本的には、公正証書で遺言を作成した方が、自筆証書遺言で遺言をするよりも、後から無効になる可能性も低く、優れている事が多いかと思います。
公正証書遺言には自筆証書遺言と異なり、証人を2人用意しなくてはならず、その証人も誰でもよいわけではなく、一定の規定があります。
公正証書遺言には、原本・正本・謄本があり、原本は公証役場で厳重に保管されます。
自筆証書遺言などは誤記があった場合に後から相続人が訂正することができません。
そのため、相続登記を行うときに不動産の表示を間違えると、法務局で不動産登記ができなくなる可能性もあります。
ですが、公正証書遺言の場合は、公証人が誤記証明を作成し簡単な誤記は訂正することができます。
ただし、事前に提出した書類などに誤りがあった場合など無制限に訂正はできませんので、その点は注意が必要です。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。



