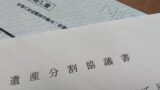日本の高齢化が進む中で平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった後に残された配偶者が長くご自宅で生活を継続することも多くなったことから、住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望される人もいます。
そこで、遺言や遺産分割協議をする際に、配偶者が無償で住み慣れた住宅に居住する権利を取得することができる権利の事を配偶者居住権といいます。
今回は、配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いや要件、期間、遺産分割協議で設定する方法や登記について解説していきたいと思います。
配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、簡単に説明すると配偶者の一方が亡くなったとき、もう一方の配偶者は、今まで住んでいた建物に継続して住むためには、法律的に、家を相続するか自宅を相続した人と賃貸借や使用貸借契約を締結する必要がありました。
実際は、親族間で賃貸借契約を結ぶケースはあまりないと思いますし、自宅を確実に相続したり、相続人に賃貸借契約を結ぶように強制することもできません。
そこで新しい制度を作り、配偶者が自宅を使用し続けられるように遺言書や遺産分割協議で、配偶者居住権を設定できるようにしました。
亡くなった人の配偶者は、亡くなった人の財産である建物に相続開始の時に居住していた場合において、一定の要件に該当すれば、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得します。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、対象外です。
(配偶者居住権)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の
全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
配偶者居住権を設定するための要件
配偶者居住権は、自宅の全部について、原則、配偶者が生きている間、無償で使用及び収益する権利を取得することができます。
要件として、配偶者が、相続開始の時点で、亡くなった方(被相続人)の財産である自宅に住んでいること、そして、遺産分割協議で配偶者居住権を設定するか、遺言書で、配偶者居住権を取得させた場合、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を設定したときです。
配偶者居住権の効果
配偶者は、善良な管理者の注意をもって、居住建物を使用収益しなくてはならず、その権利を譲渡できませんし、勝手に自宅の所有者(自宅を相続した相続人等)に承諾なく、自宅を改築や増築することもできませんし、人に貸したりすることもできません。
ただし、自宅を修繕することは可能ですが、その旨を所有者に通知しなくてはなりません。
基本的に、家を使用するために必要な費用は、配偶者が負担することになりますが、それ以外の費用は所有者に請求ができます。
家庭裁判所の手続きで配偶者居住権を取得するには
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、一定の事項に該当する限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができます。
- 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき
- 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く)
配偶者居住権の登記

配偶者居住権を第三者に対抗するためには、登記が必要です。
第三者に対抗するという意味は、簡単に言うと自分の権利を皆に主張することができるという意味だと思ってください。
自宅を所有する人(自宅を相続した相続人等)は登記に協力する義務を負うことになります。
配偶者居住権の存続期間
長期の配偶者居住権は、原則として配偶者が死亡するまでは存続しますが、遺産分割協議、遺言、または遺産分割の審判において、別段の定めをした場合と配偶者が前期の義務に違反した場合に自宅の所有者が相当の期間を定めて、是正を催告したがその期間に是正されない場合に、自宅の所有者が配偶者に対して配偶者居住権の消滅を通知したときに権利を失います。
権利を失った場合には、原状回復義務を負うことになり、通常の損傷や経年劣化以外をもとに戻さなくてはなりません。
広告
配偶者短期居住権とは

配偶者の一方が亡くなり、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に居住していた場合で亡くなった方が、第三者に遺言書で、自宅を遺贈する旨が記載されていた場合は自宅を明け渡さなくてはならないのでしょうか。
仮に自宅を直ぐに明け渡さなくていけないとなると、配偶者が高齢の場合に肉体的、精神的にも大きな負担となるため、法律で一定の期間は配偶者を保護するため、自宅の明け渡しが猶予されます。
法改正がされる前は、判例で相続開始から遺産分割時まで使用貸借契約が成立すると推認され短期的な居住権が確保されていました。
ただ、上記の場合だと第三者に財産を渡す場合など、遺言書で贈与すると記載があると、亡くなった人が配偶者に居住させる意思がなかったとして、配偶者は保護されなくなってしまい、直ぐに退去する必要がありますが、民法の改正で退去までの猶予期間が条文で設定されました。
(配偶者短期居住権)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者短期居住権の存続期間
改正民法では、生存配偶者が、亡くなった人の財産に存した自宅に相続開始(亡くなった日)の時に自宅に無償で居住していた場合には、いずれか遅い日まで、自宅を相続したり、遺贈を受けた人に対して、無償で使用する権利を主張することができます。
- 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日
- 相続開始の時から6か月を経過する日
上記以外の場合で、第三者に自宅を遺贈する旨があった場合に、第三者は生存配偶者に対して、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れができ、申し入れをした日から、6か月を経過するまでは、自宅を無償で使用することができます。
配偶者短期居住権の効果
配偶者短期居住権は、長期の配偶者居住権と同じように、使用するためには善管注意義務を負い、自宅の所有者の承諾がなければ、賃貸など第三者に使用させたりすることができませんが、修繕はすることはできます。
自宅の必要費は、配偶者が負担しますが、通常の必要費以外は、建物の所有者が負担します。
配偶者短期居住権は、上記の存続期間が経過するか、配偶者が用法遵守義務に違反したり、建物を所有者に承諾なく使わせた場合、遺産分割等で所有権を取得した場合、配偶者が亡くなった時に消滅します。
居住建物の返還
配偶者が、配偶者居住権を取得した時などを除いて、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければなりませんが、配偶者が居住建物について、共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることはできません。
配偶者短期居住権の登記について
配偶者居住権と違い、配偶者短期居住権は登記ができません。
広告
相続放棄と配偶者短期居住権
相続放棄をした場合でも、配偶者は直ちに建物を明け渡す必要はありません。
建物の所有権を取得した者から、配偶者単位居住権の消滅の申入れを受けた日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。
建物が第三者に譲渡された場合
配偶者短期居住権は登記ができないため、建物が第三者に譲渡された場合は、その第三者に対して、配偶者短期居住権を主張できませんので、注意が必要です。
配偶者は、建物を譲渡した者に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求できると考えられています。
広告
まとめ
配偶者居住権を活用することによって、今までより配偶者が自宅に引き続き住めるようになり、所有権の移転や、配偶者と相続人間で賃貸借契約を結ばなくてもよくなりました。
配偶者短期居住権に関してですが、この制度がないと、配偶者が居住している住宅が第三者に遺贈された場合、使用利益を請求される可能性もあります。
それに、突然自宅の退去を要求されることは、精神的にも肉体的にも辛いものがあるため、この制度を活用すれば、救済されるかもしれません。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。