NPO法人を設立する際、最初に直面するハードルのひとつが「10人の社員を集めること」です。「なぜ10人も必要なの?」「どうやって集めればいい?」「家族や知人でもいいの?」「失敗するとどうなる?」など、疑問や不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、法的根拠から集め方、設立のステップ、審査での注意点までを網羅的に解説します。実務に役立つ書類チェックリストや審査で見落とされがちなNG例も紹介しながら、設立を成功に導くポイントを丁寧にご案内します。
この記事でわかること
- 「10人」が必要な法的背景とその定義
- 集めるための3つの実践的な方法
- 所轄庁の審査で落ちる典型的な原因と対策
- 設立をイメージしやすくする参考シナリオ
- 設立の手順と提出書類一覧
- 設立後に注意すべきこと(会計・認定NPO化など)
- よくある質問とその回答
「10人」が必要な理由とは?法的な根拠と定義

こんな悩みを抱えていませんか?「どうして“10人”が必要なの?」その背景と意味を丁寧に解説します。
法律で定められた社員数の最低ライン
NPO法人を設立するには、特定非営利活動促進法(通称「NPO法」)により「社員(構成員)10人以上」が必要です。この「社員」は、法人格を持つ団体の構成員として、法人の最高意思決定機関である「社員総会」に出席し議決権を持つ人々のことを指します。
社員10人の定義
- 実際に活動に参加する意思があることが必要
- 同一世帯の家族ばかりでは認められない場合あり
所轄庁の審査では「形式的に集められた10人」や「名義貸し」と疑われるようなケースは認証されないこともあるため、単なる数合わせではなく、実質的な関与が求められます。
社員と役員の違い
役員は社員から選出しても構いませんが、兼任や同居・親族関係が多いと審査上不利になることもあるため、構成の多様性にも配慮しましょう。
メンバーを10人集める3つの効果的な方法

「人が集まらない…」そんな悩みを解決するための実践的な集め方をご紹介します。
① 明確なビジョンと目的を提示する
最も重要なのは「なぜこの活動をするのか?」をはっきり言語化することです。活動の背景や課題、目指す未来像が明確であればあるほど、共感を得やすくなります。
- 「家庭の経済格差で教育の機会を失う子どもをなくしたい」
- 「地域の高齢者が孤立しない町をつくりたい」
これらは説明会やSNS投稿などで一貫して発信することで、賛同者の獲得につながります。
② オンラインとオフラインを併用する
現代では、リアルな人間関係と同時にデジタルの接点を活用することが必須です。
オフラインの手法
- 地域イベントや市民活動センターでの案内
- PTAや職場、友人への声かけ
オンラインの手法
- FacebookグループやX(旧Twitter)投稿
- 無料のZoom説明会開催
- 地域向けクラウド掲示板やLINEオープンチャットの活用
③ 小規模な説明会や座談会を開催する
「設立メンバー募集説明会」「一緒にNPOを考える会」などを対面またはオンラインで実施すると、興味を持っている人と深くつながることができます。資料配布やアンケートを活用し、参加者の意欲を見極めましょう。
よくある失敗とその対策
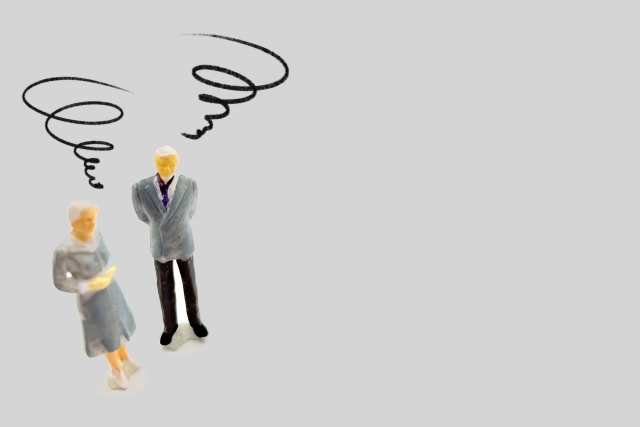
「知らなかった」では済まされない、よくある落とし穴とその回避法を解説します。
名義貸しによる認証却下
行政は「実態のある団体かどうか」を厳しくチェックしています。書類上だけで10人揃えても、事業計画の実現性やメンバーの関与度が低いと、不認証になることがあります。
対策:事前に活動意欲を確認し、役割分担やミーティングを設ける。
同一世帯・親族が多すぎる
理事3人が家族であったり、社員の大半が同居家族の場合、運営の透明性が疑われ、改善指導や認証拒否につながるケースがあります。
対策:他地域・他業種の協力者も積極的に加える。
書類不備・表現の曖昧さ
とくに設立趣旨書や定款、事業計画書の内容が不十分だと、差し戻しや不認証のリスクが高くなります。
対策:最新のガイドラインに沿ったテンプレートを使用。必要に応じて行政書士に相談。
参考シナリオ:地域学習支援NPO設立の仮想例

「本当に自分でもできるの?」と不安な方へ、具体的なイメージをつかむための参考事例をご紹介します。
※以下は、読者の理解を深めるための「参考シナリオ(架空の事例)」です。
Aさんのケース(地方都市・30代・会社員)
Aさんは地域の子どもたちが家庭環境により学習に遅れをとっている現状を見て、無料の学習支援を行うNPO法人設立を決意。
ステップ1:ビジョンを発信
Facebookで「子どもの学びを支える居場所を作りたい」と発信。友人からリアクションが集まる。
ステップ2:少人数の説明会開催
旧友やPTA関係者を中心に、オンライン説明会を2回実施し、合計10人の参加・賛同を得る。
ステップ3:法人設立
このように、明確なビジョンと小さな行動の積み重ねで、着実に設立へと進むことができます。
設立までの流れと必要な書類一覧

「何から手をつければ?」という方へ。設立までのステップと準備物を一括チェック!
設立手続きの全体フロー
- 設立趣旨書・定款の作成
- 設立総会の開催(議事録の作成)
- 所轄庁に設立認証を申請(標準処理期間:約2か月)
- 法務局で法人登記を行う
- 法人番号取得・銀行口座開設・活動開始
必要書類チェックリスト(申請時)
- 設立趣旨書
- 定款
- 設立総会議事録
- 役員名簿
- 役員就任承諾書・誓約書
- 社員名簿(10名以上)
- 事業計画書(2年分)
- 活動予算書(2年分)
これらの書類は、テンプレートを活用して整備し、形式や押印の不備がないか事前に確認しましょう。
広告
設立後に気をつけたいこと

設立後こそがスタートライン。継続的な運営と信頼のために注意すべき点を押さえましょう。
会計処理と年次報告の義務
NPO法人には、毎年「事業報告書」「財産目録」「活動計算書」などの提出義務があります。不備があると改善命令の対象になるため、早い段階で会計体制を整えることが重要です。
認定NPO法人を目指す場合
認定NPOになると、寄付金控除や法人税優遇の対象となりますが、次のような厳しい要件があります。
- 年間100人以上の寄付者がいること(例外あり)
- 適切な会計・報告体制が整っていること
- 設立から原則2年以上経過していること
まずは「普通のNPO法人」として実績を積み上げることが大切です。
よくある質問(FAQ)
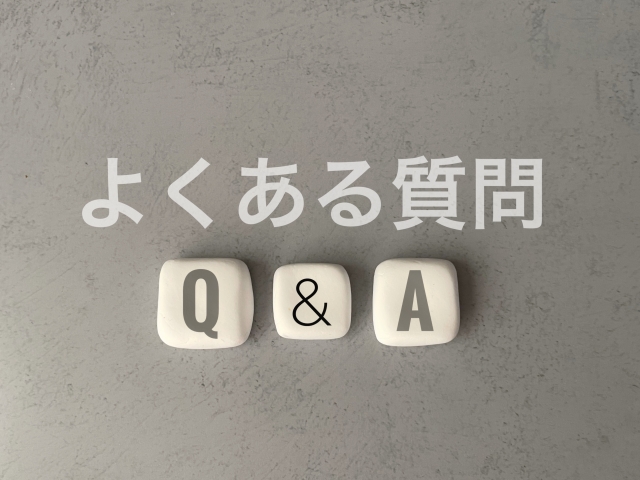
「こんなときどうするの?」にお答えします。
不安や疑問の解消にお役立てください。
Q1:家族や友人でも社員になれますか?
なれますが、社員全体の構成が家族・親族に偏りすぎないよう注意が必要です。
Q2:10人未満になったら法人解散?
即時解散ではありませんが、所轄庁への報告が必要です。追加メンバーを速やかに補充しましょう。
Q3:どうしても10人集まらないときは?
任意団体としてまずは活動を始め、実績を積んでからメンバーを増やすという選択肢もあります。
広告
まとめ
NPO法人の設立は、「社会課題を解決したい」という思いを形にする第一歩です。その中で「10人の社員を集める」というステップは、単なる数合わせではなく、共に歩む仲間を見つける大切な過程でもあります。
この記事で紹介した手順やポイント、チェックリストを参考に、まずは小さな一歩を踏み出してみてください。ビジョンに共感する人は必ずいます。あなたの一歩が、社会をより良くする確かな一歩となりますように。
相談窓口のご案内
「ひとりで全部やるのは不安…」そんな方に、無料相談をご用意しています。
行政書士への無料オンライン相談も受付中です。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。






