遺言書を作成する際には、遺留分に気を付けなくてはなりません。
遺留分は、被相続人の収入で、生計を立てている家族を保護するために設けられました。
今回の記事では、遺留分について解説しようと思います。
遺留分とは
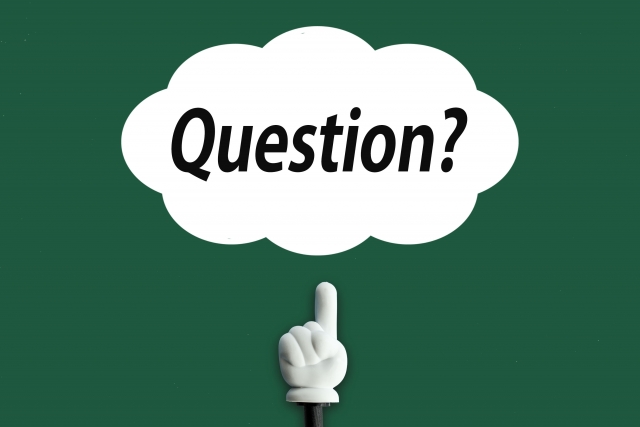
遺留分とは、簡単に言うと、亡くなった人が有していた財産について、一定の割合を法定相続人に保証するというものです。(兄弟姉妹に遺留分はありません)
遺留分を有する相続人は、相続放棄とは違い、相続の開始前でも行うことができます。
遺留分で保障される割合
遺留分は、法定相続分と違い全ての相続人に適用されるわけではなく、独立した生計を立てているであろう兄弟姉妹には、遺留分がありません。
総体的遺留分の割合
1.直系尊属のみが相続人である場合
亡くなった方(被相続人)の財産の3分の1
2.上記以外の場合
亡くなった方(被相続人)の財産の2分の1
個別的遺留分の割合
個別的遺留分は、総体的遺留分の割合に乗じたものとなります。
例えば、3000万円の相続財産があった場合は、配偶者は750万、子供が3人いる場合は、各250万円となります。
3000万円×2分の1×2分の1=750万円
3000万円×2分の1×2分の1×3分の1=250万円
広告
遺留分を侵害された場合はどうすればよいのか
遺留分を侵害される遺言などがあった場合で遺留分を主張したい場合は、遺留分侵害額請求権の行使をすることになります。
※民法改正前は遺留分減殺請求権と言いました。
遺留分を請求できる者
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子供、直系尊属(親)に権利がありますが、胎児、代襲相続人は遺留分がありますので注意が必要です。
遺留分の時効について
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも同様です。
遺言がある場合とない場合の手続きの違い

相続の手続きで、遺言がある場合とない場合とでは、手続きが変わります。
遺言書がない場合は、基本的に相続人で話し合いをして、内容に折り合いがつけば、遺産分割協議書に相続人が署名押印をして遺産を承継します。
遺言があった場合は、基本的に遺言書に記載のあるとおりに遺産が承継されることとなり、遺言書の内容では、全く財産を受け取ることができなくなってしまいます。
それでは、配偶者やその子供など、亡くなった方の収入で生活していた方は、急に収入を失い生活ができなくなってしまいます。
そのため、法律で保護することになった制度が遺留分です。
広告
遺留分を放棄するにはどうすればよいのか
遺留分を有する相続人は、相続放棄とは違い、相続の開始前でも行うことができます。
手続きとしては、相続放棄と同じで家庭裁判所で手続きを行い、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
遺留分の放棄で勘違いしてしまうのですが、相続権を失うわけではないので、遺言書を作成しておかないと法定相続分に従い相続してしまうことになります。
相続開始前に遺留分を放棄する場合、亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所の許可を必要とします。
相続放棄の時と同じように、家庭裁判所は遺留分を放棄するのが本当にその人の意思なのか(強迫されていないか)を確認し、遺留分を放棄するにあたり、放棄と引き換えになる代償があるか、遺留分を放棄する理由に合理性・必要性があるかを判断して許可するかを決めます。
(遺留分の放棄)
民法 – e-Gov法令検索より引用
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
なぜ家庭裁判所で手続きが必要か
遺留分は法定相続人(兄弟姉妹を除く)の財産的な権利ですので、この権利をどうするかは相続人の自由です。
法律を作る際に、財産を持っている親が、強制的に放棄させる可能性もあることを考え、遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所で厳格な手続きを必要としました。
相続開始後の遺留分放棄
相続が開始した後は、亡くなった方が(被相続人)生きてる場合と違い、自由に放棄することができます。
相続分の放棄

相続人が相続した後に、遺産分割協議を行うのですが、その際に、遺産を取得しないことを相続分の放棄といいます。
相続放棄とは違い、相続人としての地位は失わない為、後日、債権者から借金の返済を請求されたら、その負担を拒否することができません。
なので、確実に財産を拒否したい場合は相続放棄をすることをお勧めいたします。
遺贈の放棄とは
遺言書で財産を遺贈すると記載されている場合、それを放棄することができます。
遺贈された人が相続人であった場合は遺贈のみを放棄することができ、相続権は失いません。
遺贈される予定だった財産は、相続の対象となりますので、改めて相続の対象となりますので、遺産分割協議で誰に取得するかを決めます。
広告
遺留分減殺請求権の変更と内容
遺言書で、遺贈や贈与などで、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人等は、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分権利者(遺留分を侵害された人)の侵害を限度で失効し、その限度で、遺言書などで遺贈された財産を取り戻すことができる制度でした。
遺留分減殺請求権の問題点
遺留分減殺請求権を行使されると、遺贈を受けたものは、遺留分を侵害された法定相続人などに、遺贈を受けた物を返還するか、遺留分侵害額の価格を支払うか選択するものとされ、仮に選択しないときは、遺留分を侵害された法定相続人などは、遺留分侵害額の価格を支払うように請求ができませんでした。
そうなると、不動産などを法定相続人と、受遺者(遺贈を受けた人)が共有してしまうことになり、権利がややこしくなり、お互い持ち分を共有していることになるので、不動産を売却したりすることが、困難になりました。
遺留分とは、例えば大黒柱のお父さんが亡くなった場合、その扶養となっている家族は、生活資金を絶たれ、生活ができなくなってしまいます。そのため、法定相続人に一定の金額を保障するための法律です。(相続分の確保)
そのため、最低限の生活資金の確保ができれば良く、遺贈したものを引き渡すよう請求する必要がそのそも必要でないという考えがありました。
なので、今回の法改正で遺留分制度が改正となりました。
遺留分侵害額請求権とは改正点
上記の問題点から、遺留分侵害額請求では、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるとされ、遺贈された物(例えば家や宝石等)を返還できなくなりました。
遺留分侵害額請求を行使された場合、直ぐに支払えない場合もあるので、裁判所は支払いに期限を与えることができることになったので、家などの大きな金額を遺贈された場合は、この制度を使うようにしましょう。
遺産をもらったものが負担する順番
遺留分侵害額請求の行使を請求されたものは、金銭債務を負担することになりますが、遺産を譲り受けた者が多い場合次の順番で負担することになります。
1.受遺者(遺贈)と受贈者(贈与)があるときは受遺者が先に負担する
2.受遺者が複数ある時は受贈者が複数ある 場合でその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的物の価格の割合に応じて負担する。
3.受贈者が複数ある時は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します。
少し、難しいかもしれませんが、簡単に言うと受贈者は贈与契約などで財産を譲り受けた人、受遺者とは、遺言などで贈与を受けた者をいいます。
広告
まとめ
相続手続きは、戸籍収集や提出する書類などが複雑でご自身で手続きをするのは難しいと思います。
当事務所では手続きを代行しておりますので、なるべく早い段階でご相談することをお勧め致します。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。




