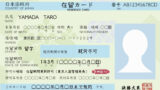日本で外国人を雇用したい企業や、日本で働きたいと考えている外国人にとって、在留資格の手続きは避けて通れない重要な手続きです。しかし、これらの手続きは非常に煩雑で、時間と労力を要します。そんな中、行政書士が行うことができる「申請取次制度」は、外国人本人が出頭することなく手続きを進めることができる非常に便利な制度です。本記事では、申請取次制度の基本から具体的な手続きの流れ、そしてそのメリットについて詳しく解説します。企業の担当者や外国人労働者が安心して手続きを進められるよう、ぜひ参考にしてください。
申請取次制度とは何か?

日本で在留資格の変更、更新、取得などの手続きを行う際、外国人本人が地方出入国在留管理官署に出頭する必要があります。しかし、これらの手続きは非常に煩雑で、外国人本人にとって大きな負担となることが少なくありません。ここで役立つのが「申請取次制度」です。この制度を利用することで、行政書士や特定の職員が外国人本人に代わって手続きを行い、本人が出頭する必要がなくなります。
行政書士が関与する理由とその重要性
行政書士が申請取次制度に関与する理由は、外国人本人が手続きを行う時間的・言語的な負担を軽減するためです。日本の法律や規則に精通した行政書士が手続きを代行することで、正確かつ迅速に進めることができます。これにより、申請の遅延やミスを防ぎ、外国人やその雇用主の安心感を高めることができます。また、行政書士は出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)とのコミュニケーションを円滑に行う役割も担い、手続き全体を効率化します。
広告
申請取次制度の対象者

申請取次制度の対象者は以下の通りです。
外国人の雇用を考えている企業
日本では多くの企業が外国人労働者を雇用していますが、在留資格の手続きは企業にとっても大きな負担となることがあります。特に中小企業や外国人雇用の経験が少ない企業にとって、手続きの煩雑さや言語の壁は大きな課題です。申請取次制度を利用することで、企業は行政書士に手続きを任せることができ、スムーズに外国人を雇用することが可能となります。
日本で働きたい外国人
日本で働きたい外国人にとって、在留資格の手続きは大きな障壁となります。日本の法律や規則を理解することは容易ではなく、手続きに必要な書類を揃えることも難しいことがあります。申請取次制度を活用することで、行政書士が手続きを代行し、外国人本人は仕事や生活に集中することができます。
申請取次制度を利用できる人々
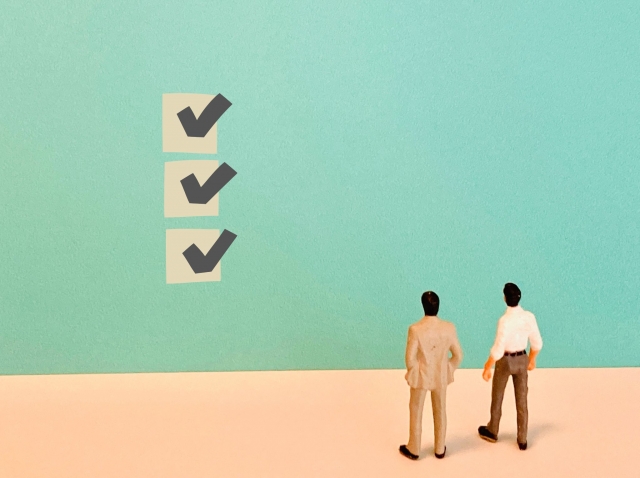
申請取次制度を利用できるのは、行政書士以外にも以下のような一定の条件を満たす人々です。
企業、学校等の職員
申請人である外国人が経営している、若しくは雇用されている機関の職員や、研修若しくは教育を受けている機関の職員が申請取次を行うことができます。具体的には以下のような人が該当します。
- 外国人が雇用されている企業の担当者
- 外国人が在籍している学校の職員
旅行業者
外国人の旅行や短期滞在に関連する手続きを行う場合、申請取次が認められている旅行業者の職員も申請取次を行うことができます。これには、旅行会社の担当者が含まれます。
公益財団法人・公益社団法人の職員
外国人の円滑な受け入れを図ることを目的として設立された公益財団法人や公益社団法人の職員も申請取次を行うことができます。これには、以下のような組織の職員が含まれます。
- 国際交流協会の職員
- 外国人支援団体の職員
弁護士
行政書士と同様に、弁護士も申請取次を行うことができます。弁護士は法的な専門知識を活かして、外国人の在留資格に関する手続きをサポートします。
広告
申請取次制度の具体的な手続き
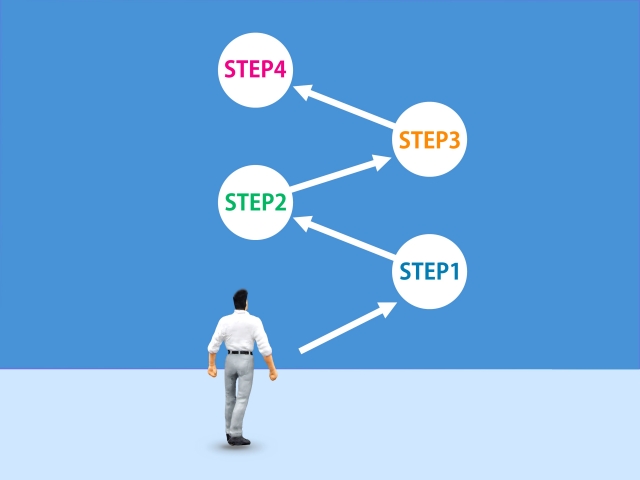
申請取次制度の具体的な手続きは以下の通りです。
必要な書類と提出方法
申請取次制度を利用する際には、必要な書類を揃えることが重要です。状況によって提出する書類は異なりますが主に、以下のような書類が必要となります。
- 在留資格に関する申請書
- パスポート
- 証明写真
- 雇用契約書(雇用の場合)
- 学歴や職歴を証明する書類
これらの書類は、行政書士が確認し、適切に整理して地方出入国在留管理官署に提出します。提出方法は、オンライン申請などがあり、行政書士が最適な方法を選びます。
申請の流れと期間
申請の流れは以下の通りです。
- 外国人本人または雇用主が行政書士に相談
- 必要書類の準備と確認
- 行政書士が地方出入国在留管理官署に申請
- 地方出入国在留管理官署での審査
- 審査結果の通知と書類の受け取り
申請から結果通知までの期間は、通常2ヶ月から3ヶ月程度です。ただし、申請内容や混雑状況によっては、それ以上の時間がかかることもあります。
行政書士の役割とサポート内容
行政書士は以下のサポートを提供します。
- 必要書類の準備と確認
- 申請書類の作成と提出
- 地方出入国在留管理官署との連絡
- 審査結果の通知とフォローアップ
行政書士は、外国人やその雇用主にとって信頼できるパートナーとして、手続き全体をサポートします。
申請取次制度のメリット

申請取次制度のメリットは以下の通りです。
外国人雇用企業にとってのメリット
企業にとっての主なメリットは以下の通りです。
- 手続きの簡略化と時間の節約
- 法的リスクの軽減
- 専門家による安心のサポート
申請取次制度を利用することで、企業は手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。特に中小企業にとっては、大きな負担軽減となります。また、行政書士が手続きを行うことで、法的リスクを最小限に抑えることができ、安心して外国人を雇用することができます。
外国人労働者にとってのメリット
外国人労働者にとっての主なメリットは以下の通りです。
- 手続きの煩雑さからの解放
- 言語の壁を超えたサポート
- 正確で迅速な手続き
申請取次制度を利用することで、外国人労働者は煩雑な手続きから解放されます。また、言語の壁を感じることなく、専門家のサポートを受けることができるため、安心して手続きを進めることができます。
申請取次制度に関する一般的な質問

申請取次制度に関する一般的な質問は以下の通りです。
申請取次制度を利用するための費用はどれくらいですか?
費用は行政書士によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度です。具体的な費用は、申請内容や必要な手続きによって異なるため、事前に見積もりを依頼することが重要です。
申請取次制度を利用することで、必ず在留資格が取得できるのでしょうか?
必ずしも取得できるわけではありませんが、専門家のサポートにより成功率は高まります。行政書士は、手続きの正確さや必要書類の揃え方について専門的な知識を持っているため、成功の可能性が高まります。
広告
まとめ
申請取次制度は、外国人やその雇用主にとって非常に有益な制度です。手続きを専門家に任せることで、煩雑な手続きを避け、業務や生活に専念することができます。特に、外国人雇用を考えている企業や日本で働きたい外国人にとって、申請取次制度は大きな助けとなります。
今後も、外国人の受け入れが進む中で、申請取次制度の利用はますます重要になるでしょう。行政書士の役割はますます大きくなり、制度の発展とともにさらなるサポートが期待されます。企業や外国人労働者は、申請取次制度を活用して、円滑な手続きを進めることが求められます。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。