2025年6月1日、厚生労働省による労働安全衛生規則の改正が施行され、建設業をはじめとする高温環境下での屋外作業等において、熱中症対策が法的に義務化されます。
これまでも熱中症対策は“努力義務”として求められていましたが、近年の気候変動に伴い、重篤な労働災害が多発。ついに、事業者に対して具体的な報告体制の整備や悪化防止措置の実施・周知といった義務が明確に課されることとなりました。
この記事では、この新たな義務内容を正確に理解し、適切に対応するための情報を整理するとともに、行政書士がどのように事業者を支援できるのかをご紹介します。
改正の背景 なぜ義務化されたのか

猛暑の影響で、毎年多くの労働者が熱中症により倒れ、最悪の場合は命を落とすケースも発生しています。特に建設業、製造業、運送業、警備業といった屋外または高温多湿環境での長時間作業を伴う業種では、熱中症のリスクが極めて高いのが現実です。
また、近年では40度近い気温が続く日も増えており、これまでの常識では通用しないレベルの暑さへの対応が求められています。こうした現状を受け、国は法令に基づく強制的な対策を通じて、労働災害の未然防止を図ることに踏み切ったのです。
広告
義務化の対象条件

今回の法改正では、以下の条件下で行われる作業において、熱中症対策が義務づけられます。
■ 環境条件
- WBGT(暑さ指数)28℃以上
- または 気温が31℃以上
WBGTは、気温・湿度・輻射熱を総合的に評価した「暑さ」の指標で、実際の熱中症リスクを的確に把握できる方法として広く採用されています。
■ 作業時間条件
- 連続して1時間以上の作業
- または 1日あたり4時間を超える作業
これらの条件に該当する場合、事業者は法的に熱中症対策を講じる義務を負うことになります。
■ 該当業務の例
- 建設現場(屋外建設作業、解体、足場組立など)
- 屋内高温作業(工場、倉庫内の荷役など)
- 警備業務(屋外交通誘導など)
- 配送業務(長時間運転、荷降ろし含む)
- 農林水産業(屋外での作業全般)
広告
事業者に求められる基本の対策フロー
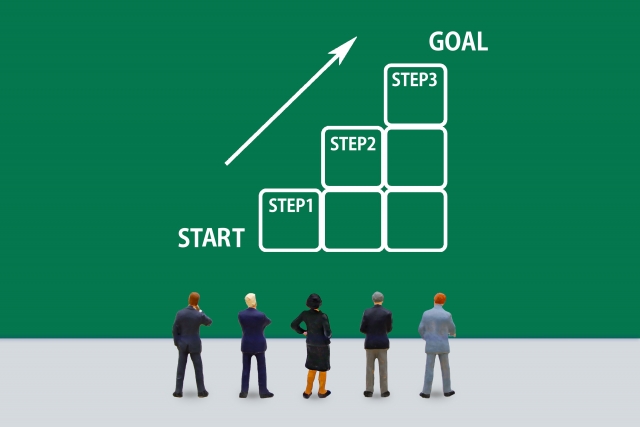
新たに義務化された熱中症対策では、次の3つのポイントが重要です。
自覚症状の早期発見・報告体制の整備
作業員が「頭痛」「めまい」「吐き気」などの初期症状を感じた場合に即時に報告できる体制を整える必要があります。
- 作業開始前の体調確認
- 定期的な声掛け・巡視
- 報告しやすい風土の醸成
熱中症発症時の悪化防止措置の実施
実際に症状が見られた場合には、即座に作業から離脱させ、次のような対応を実施します。
- 涼しい場所での安静
- 体を冷やす(冷却シート、氷水等)
- 水分・塩分の補給
- 必要に応じて医師の診察や救急搬送
この一連の流れを手順書として文書化し、現場に周知することが必要です。
教育・訓練と記録の徹底
上記の対策は、単に用意するだけでなく、現場の全員に対して教育・訓練を実施し、その記録を管理することが求められます。
多主体で進める現場連携のポイント

「元請と下請、警備会社…誰がどこまで対応すべき?」そんな現場の疑問に答える連携の考え方を整理します。
共同で実施すべき事項
- 対策マニュアル・手順書の共有
- 作業条件の把握とリスク評価
- 休憩所・給水場所の共用
- 情報伝達・報告ルートの明確化
契約書や見積書への反映
事業者は、熱中症対策に必要な費用や人員、設備の負担についても、契約書・見積書に明示的に記載しておくことが推奨されます。たとえば。
「冷却設備の設置費用」
「WBGT計測のための人員配置」
「対策講習の実施費」
これにより、トラブルや責任の所在が不明確になるのを未然に防ぐことができます。
業種・役割別の具体的対策事例
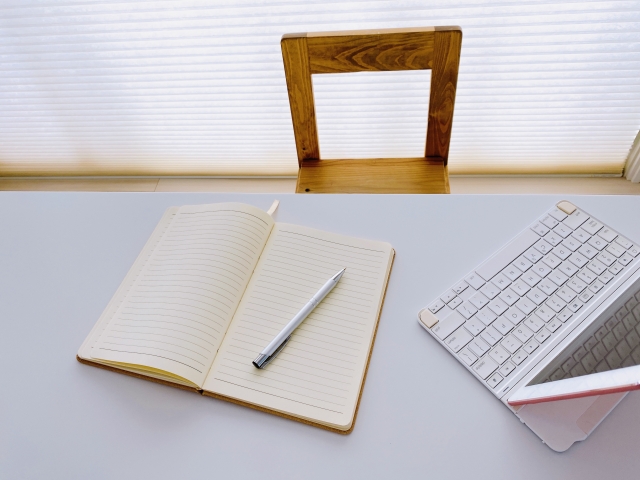
「うちの業種では、どんな対策が必要なんだろう?」
建設業、警備業、配送業などの現場別に、実践的な対応例をまとめました。
■ 建設業
- WBGT測定器の常設と数値の掲示
- 1時間ごとの定期休憩
- 日陰スペースや空調設備の整備
- 水分・塩分補給所の設置
■ 警備業
- 座哨警備の時間制限(15〜20分ごとの交代)
- ファン付き制服や遮熱素材の導入
- 交代要員の確保と待機体制の整備
■ 配送業・農作業等
- 長時間運転による車内温度上昇対策(遮光、エアコン)
- 作業スケジュールの柔軟化(早朝作業の導入)
- 携行型水分・塩分補給ツールの使用
広告
国・自治体キャンペーンと助成金活用

「対策にコストがかかるのが心配…」
国や自治体が提供するキャンペーンや補助制度を上手に活用しましょう。
厚労省は毎年キャンペーンを実施しており、対策手順やチェックリスト、ポスター等が無償で提供されています。
また、自治体によっては以下のような支援策があります。
- 熱中症対策用品(冷却ベスト、WBGT計)の購入補助
- 安全教育にかかる研修費の助成
- 中小企業向けの設備導入補助金
こうした制度を積極的に活用することが、コストを抑えつつ効果的な対策を進める鍵となります。
行政書士が支援できる5つのポイント
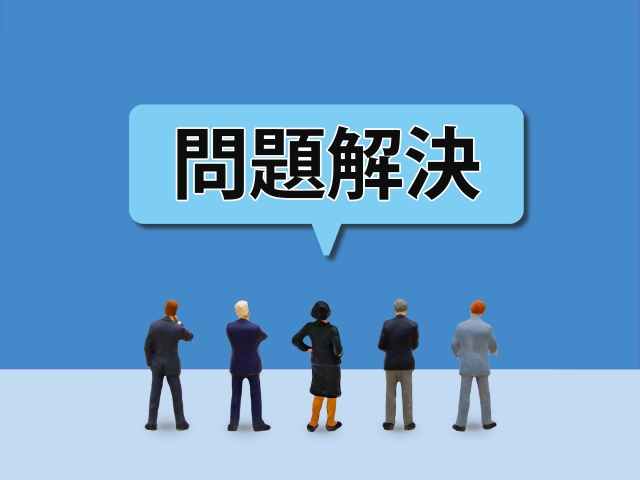
「行政書士に何を頼めるのかよく分からない…」
文書作成・契約支援・監査対応など、建設業者を支える具体的な業務を紹介します。
行政書士は、法改正に関する文書整備と体制づくりの専門家として、以下の支援を行うことが可能です。
- 熱中症対策計画書・報告体制図の作成支援
→ 作業現場の特性に応じたカスタムプランの提案 - 契約書・見積書への明記内容の整理支援
→ 法的根拠に基づいた契約上の注意点をアドバイス - 元請・下請・関係会社間の合意文書作成支援
→ 責任分担や連携ルールの明文化によるリスク回避 - 教育マニュアル・チェックリストの作成支援
→ 作業員への理解浸透を助ける書類の整備 - 対策実施記録・監査対応書類の管理支援
→ 労基署などの監査時に備えた実務書類の整理
よくある質問(FAQ)
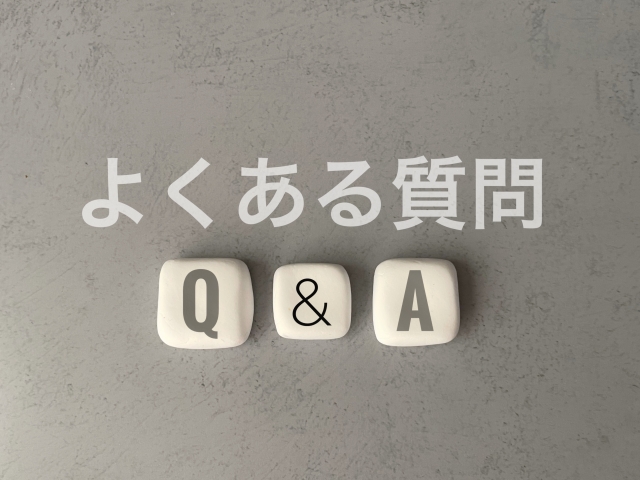
「対象条件は?」「罰則は?」など、よく聞かれる疑問にスッキリお答えします。
すべての建設現場が対象になりますか?
WBGT28℃以上、または気温31℃以上の環境での作業が対象です。ただし、それ未満でも予防的措置を講じることが強く推奨されています。
違反した場合の罰則はありますか?
労働安全衛生法に基づき、行政指導・命令・罰金等の処分対象となる可能性があります。実際に熱中症による事故が発生した場合は、事業者責任が重大視されます。
警備員や運送業者も対象になりますか?
屋外作業や長時間車内に滞在する業務も条件次第で対象です。特に警備業務は、別途留意点が厚労省から示されています。
広告
まとめ 早期対応の呼びかけと行政書士活用のメリット
熱中症対策義務化は、単なる“安全対策”にとどまらず、法令遵守・労務管理・契約対応を含む多角的な対応が求められる分野です。
早めに計画を立て、社内体制や契約文書を整えておくことで、夏場のリスクを大幅に軽減できます。
行政書士は、こうした複雑な法改正対応において、実務と法令の橋渡し役として企業を強力にサポートできます。ぜひお気軽にご相談ください。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。




